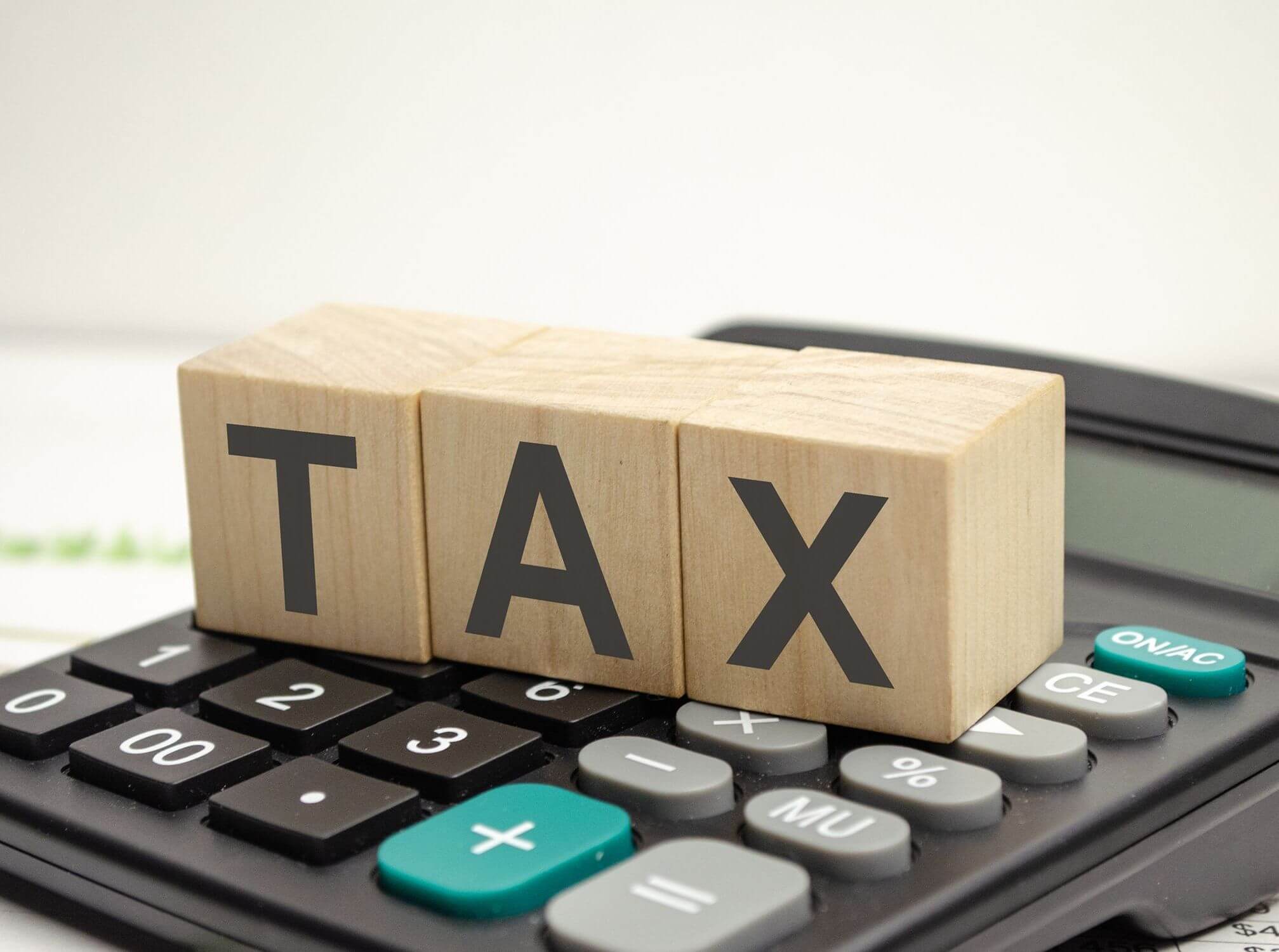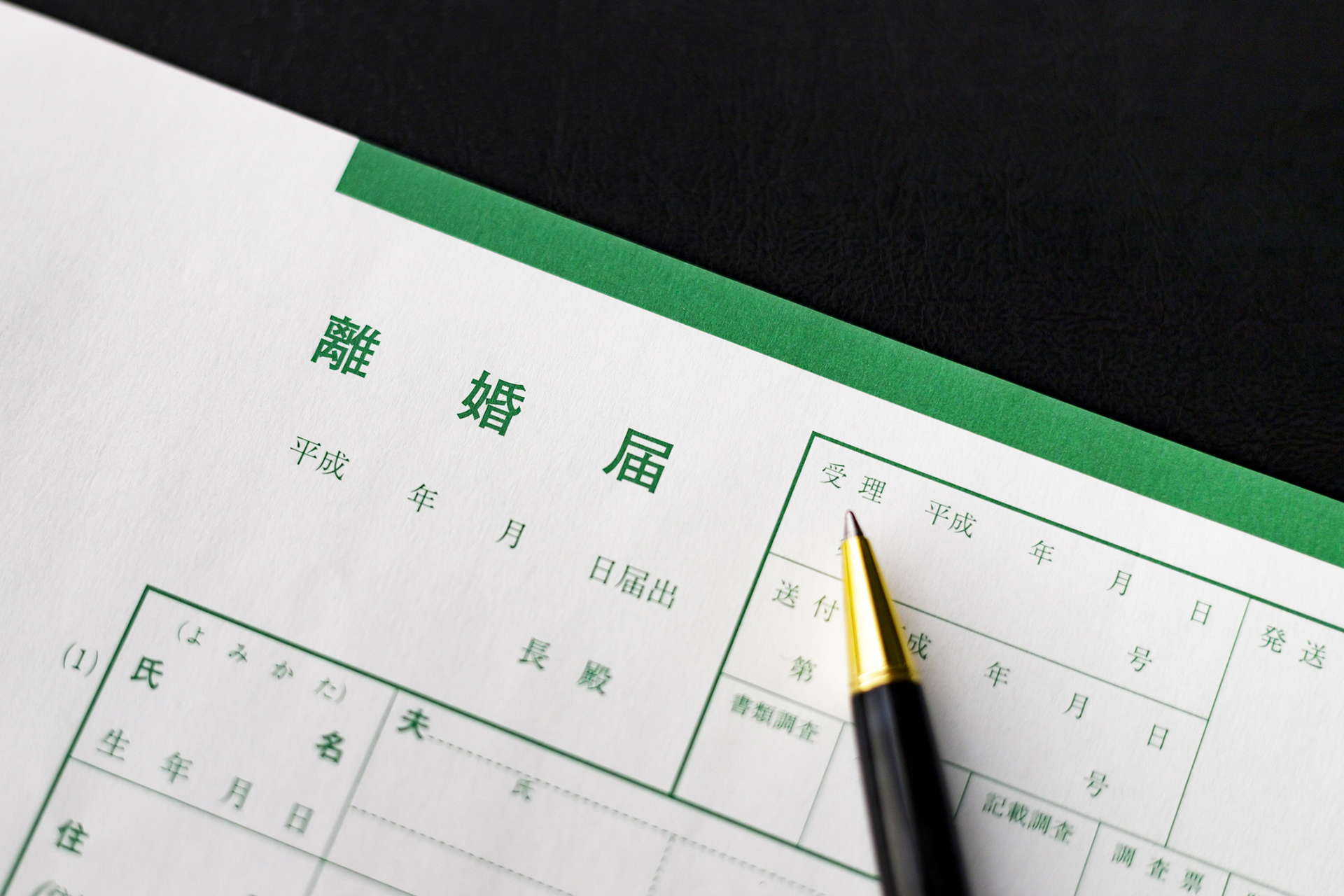不動産売却時にかかる税金や譲渡所得で利用できる特例
不動産を売却する際には、さまざまな税金や特例が関わってきます。税金の支払いを最小限に抑える方法や特例の活用法を知っておくと、売却時の負担が軽減されます。この記事では、不動産売却に伴う税金や利用できる特例について詳しく解説します。
1.不動産売却時にかかる税金

不動産を売却する時には、さまざまな税金がかかります。詳しくみてみましょう
| 取引金額 | 不動産売買契約書 |
| 1万円未満のもの | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 500円 |
| 100万円超200万円以下 | 1,000円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 160,000円 |
| 10億超50億円以下 | 320,000円 |
| 50億円超 | 480,000円 |
| 記載金額なし | 200円 |
契約書に記載されている「契約書貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとする」という記載は、売主と買主が印紙代を平等に負担することを意味しています。 しかし、実際の負担方法には、以下の2つのケースがあります。
a.契約書原本を2部作成し、売主・買主がそれぞれ印紙代を負担
この場合、契約書の原本が2部作成され、売主と買主がそれぞれの原本に必要な印紙を貼付し、印紙代を負担します。
b.契約書原本を1部作成し、原本を保管する方が印紙代を負担
この場合、契約書の原本は1部作成され、通常は不動産取引の仲介業者や弁護士などが原本を保管します。この場合、原本を保管する側が印紙代を負担することが一般的です。
これらの方法は、不動産取引における慣習や契約の条件によって異なることがあります。契約書の作成や印紙代の負担については、売主と買主が合意し、契約書に明記されることが重要です。
2. 仲介手数料の消費税
仲介手数料は、売買価格に応じた料率が宅地建物取引業法で定められており、売買契約成立時には売買価格の3%に加えて6万円、そして消費税がかかります。
支払うタイミングは、売買契約成立時に50%、残りの50%は引き渡し完了時に支払われます。
仲介手数料は宅地建物取引業法で以下のように上限が定められています。
| 売買価格(税込) | 料率(税抜) |
| 200万円以下の部分 | 5% |
| 200万円超400万円以下の部分 | 4% |
| 400万円超 | 3% |
たとえば、不動産の売買価格が400万円を超える場合は、上限料率が3%となりますので、計算式は「仲介手数料=売買価格×3%+6万円+消費税」となります。
売主が物件を売却する際には、抵当権が設定されている場合、売却資金でその抵当権を解消するために「抵当権抹消登記」が必要です。この手続きは、売主の権利を買主に譲渡する前に行われます。通常、抵当権抹消登記と所有権移転登記は決済日に一緒に行われます。また、売主の住所が変更されている場合には「住所変更登記」も必要です。
抵当権抹消登記の場合、登録免許税の費用は1物件につき1,000円です。1物件とは、土地が1筆であり、建物が1つの建物である場合を指します。たとえば、一戸建ての場合、土地と建物2件分の登録免許税がかかります。登録免許税の支払いは、登記申請時に司法書士の報酬と一緒に請求され、指定された金額の印紙を貼ることで印紙税も納められます。
4. 譲渡所得税
不動産を売却する際には、売却益に譲渡所得税がかかります。売却益が発生していた場合は確定申告を行い、納税をしましょう。計算方法は次項で詳しく解説します。
2.譲渡所得税の計算方法

譲渡所得は、売却時の価格ではなく、取得費用と売却費用を売却金額から差し引いて算出されます。この章では、譲渡所得税の計算方法を解説します。
建物取得費の計算式は以下のようになります。
建物取得費 = 建物の購入価額 – 減価償却費相当額
減価償却費は以下の式で計算されます。
建物の購入価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
建物の償却率は、建物の構造によって異なります。木造の場合は0.031、鉄筋・鉄骨コンクリート造の場合は0.015が一般的です。
なお、購入価格が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として申告します。たとえば、2,000万円で家を売却した場合、概算取得費は100万円となります。
| 売却益(譲渡所得)= 売却価格 売却価格から以下の3つの費用を差し引く ① 物件の購入価格から減価償却費※を引いた価格(購入したときの価格) ② 購入したときの費用(取得費) ③ 売却したときの費用(譲渡費) |
減価償却費 = 建物購入価額×0.9×償却率×経過年数 (経過年数は築年数ではなく、購入の引渡から売却の引渡までの所有期間を表します) 売却価格とは、家やマンションなどの不動産が売却された際の金額を指します。
取得費は、不動産を購入する際に支払った費用を指します。具体的には、土地や建物の購入価格、建築費用、手数料、税金などが含まれます。ただし、建物の場合は経年劣化による価値の減少を考慮するため、減価償却を考慮する必要があります。
譲渡費は、不動産を売却時に発生した費用を指します。仲介手数料や印紙税、土地の測量費用、建物の解体費用などが該当します。
譲渡所得にかかる所得税と住民税は、不動産売却した年の1月1日現在の所有期間(その不動産を所有していた期間が5年以下か5年超か)で変わってきます。
| 不動産を所有していた期間 | |||
| 区分 | 短期 | 長期 | |
| 期間 | 5年以下 | 5年超 | 10年超所有軽減税率の特例 |
| 居住用 | 39.63% 所得税30.63% 住民税 9% | 20.315% 所得税5.315% 住民税 5% | ①課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%) ②課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |
| 非居住用 | 39.63% 所得税30.63% 住民税 9% | 20.315% 所得税15.315% 住民税 5% | |
※2013年から2037年までは復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算されます
不動産の所有期間によっては所得税と住民税が大きく変わってしまうため、売却するタイミングに注意しましょう。
3.譲渡所得で利用できる特例

次に、譲渡所得で利用できる特例をいくつかご紹介します。
譲渡所得から最大3,000万円まで控除を受けることができる特例です。
特別控除を利用する際には、いくつかの注意点があります。
まず、今住んでいる住宅を売却して3,000万円の特別控除を利用して新たに住宅を購入する場合、住宅ローン控除は使用できません。
次に、特例を適用するためには、売却される不動産が所有者の居住用である必要があります。所有者が住んでいた住宅であっても、一定期間が経過すると特例が適用されません。
最後に、通常、相続したマイホームには特例が適用されません。ただし、要件を満たしていれば相続した住宅でも「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」という特例を利用することができます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2. 所有期間10年超の物件に対する軽減税率の特例
この特例は、自らの居住用のマイホームを売却した際に適用され、一定の要件を満たすことで長期譲渡所得税の税率を軽減するものです。
特例を受けるための基本的な要件は、売却物件が自分の居住用財産であり、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていることです。
通常、長期譲渡所得に対する税率は20.315%ですが、この特例を利用すると、課税譲渡所得の最初の6,000万円までが14.21%まで軽減されます。ただし、6,000万円を超える部分については通常の税率が適用されます。
詳細は以下のとおりです。
| 譲渡所得 | 所得税 | 住民税 | 合 計 |
課税譲渡所得が 6,000万円以下 | 10.21% | 4% | 14.21% |
| 譲渡所得 | 所得税 | 住民税 | 合 計 |
課税譲渡所得が 6,000万円超(6,000万円以下の部分) | 10.21% | 4% | 14.21% |
課税譲渡所得が 6,000万円超(6,000万円超の部分) | 15.315% | 5% | 20.315% |
なお、この特例は「3,000万円の特別控除の特例」と併用可能です。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
4.売却でかかる税金の納付時期や納付方法
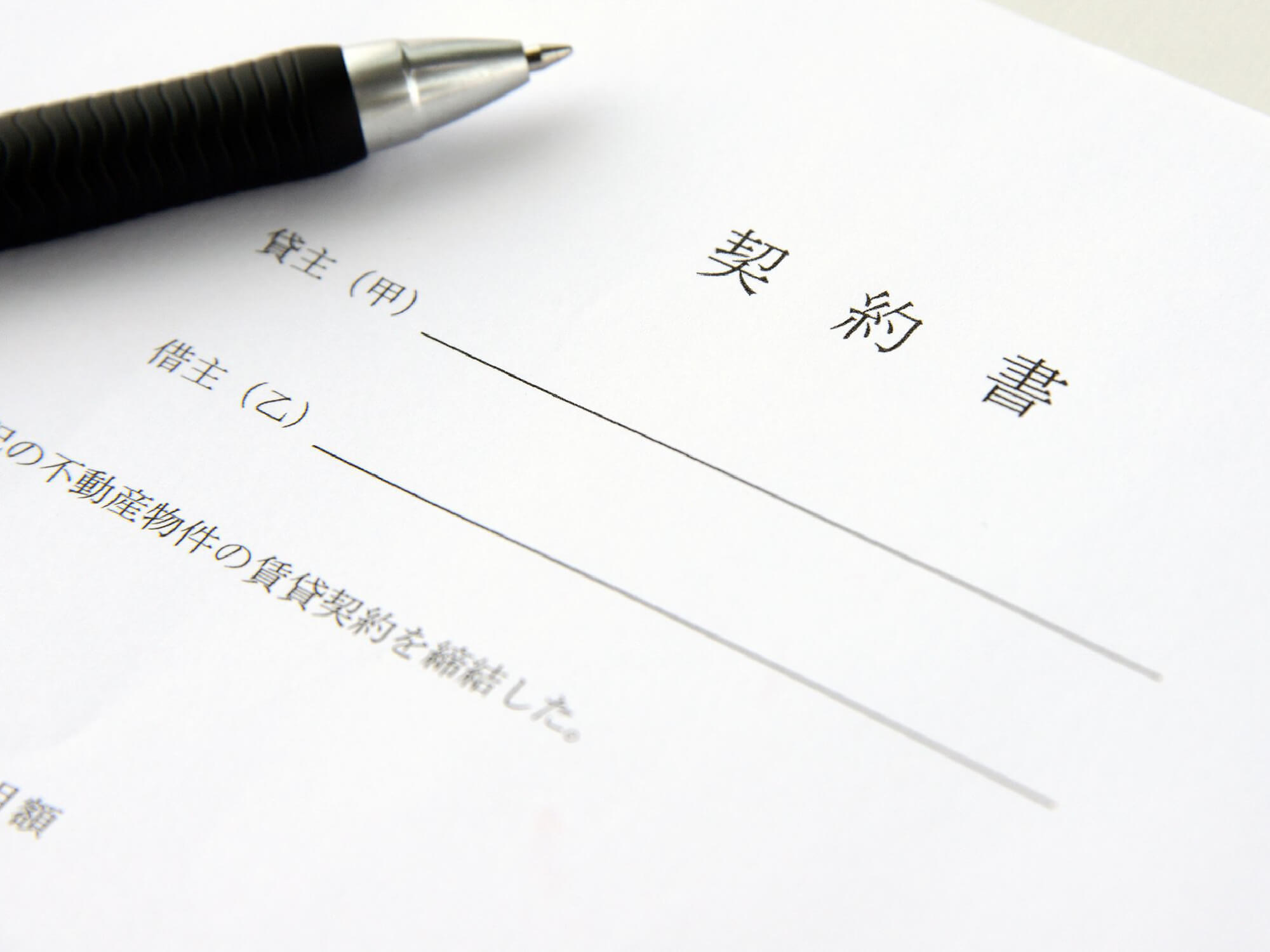
不動産を売却して譲渡所得が生じた場合、確定申告が必要になります。
確定申告の計算期間は1月1日から12月31日までの1年間です。必要な書類を用意して、2月15日から3月15日の間に提出しましょう。
◎確定申告の手順
1.課税譲渡所得を計算する。
2.必要書類を準備する。
3.確定申告書を作成する。
4.税務署に訪問するか、電子申告で手続きを行う。
5.納税か還付を受ける
申告書を提出した後は、還付を受けるか、納税します。還付を受ける場合は、申告書に記入した金融機関の口座に振り込まれます。
◎納税の方法
・振替納税を利用する
・現金で納付する
・国税電子申告・納税システム(e-Tax)で納付する
・クレジットカードで納付する
◎確定申告に必要な書類
・譲渡所得の内訳書…不動産の概要や売却金額、費用などを記載した書類。税務署から送付されるので、記入して提出します。
・譲渡時の書類…売買契約書や売買代金受領書、固定資産税精算書、仲介手数料の領収書などのコピー。
・取得時の資料…不動産を取得した際の売買契約書や固定資産税精算書、仲介手数料の領収書などのコピー。
・売却した不動産の全部事項証明書…法務局で入手できます。特例の申告では原本の提出は必要ありません。
5.まとめ
不動産売却にはさまざまな税金がかかりますが、売利益が発生した場合は確定申告を行い、納税をしましょう。節税については、譲渡所得で利用できる特例を活用することで負担を軽減できます。不動産売却を検討している方は、この特例を上手に活用して節税のポイントを押さえることが重要です。
コラム・住まい探しに役立つ情報
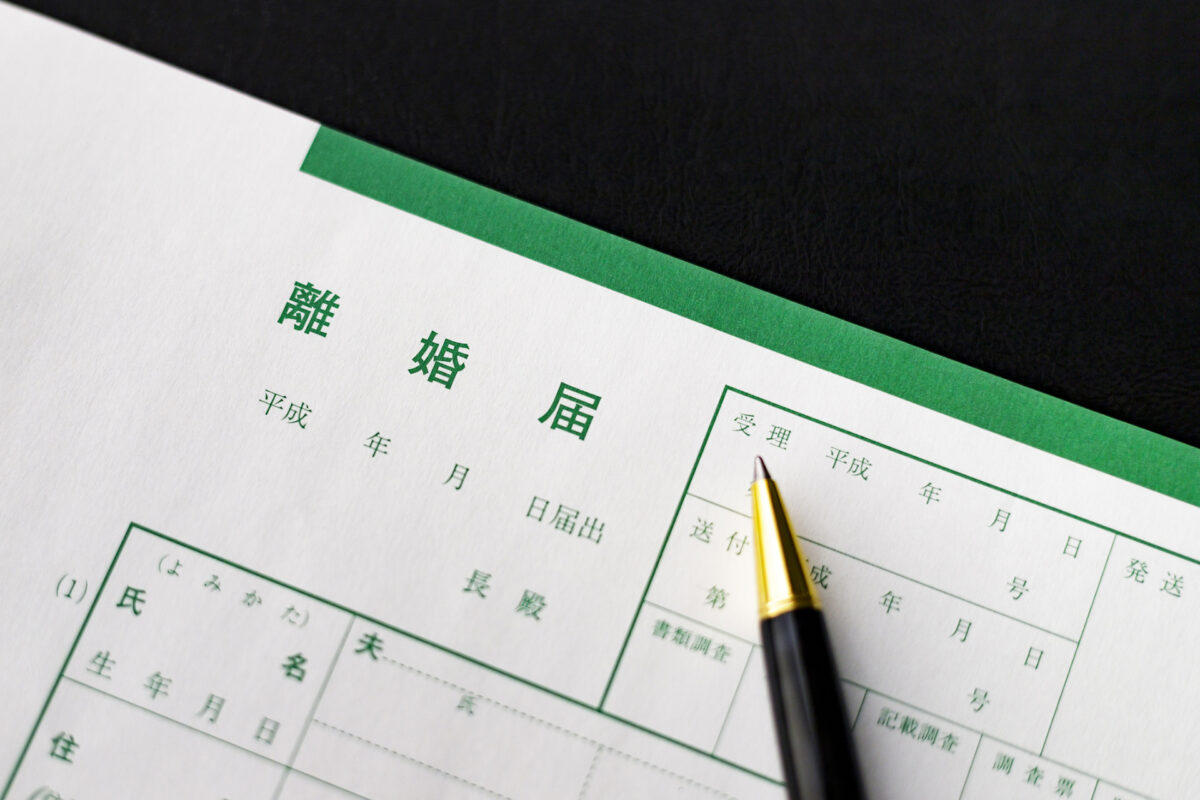
離婚で家を売却するメリットやタイミング、売却する時の手順について
離婚が決まると、夫婦の共有財産の分与が必要になります。その中でも不動産(家)の分割は、特に慎重に進めるべき重要な問題です。この記事では、離婚時における家の売却メリットや最適なタイミング、また売却をする時の手順について詳しく解説します。
1.離婚で家を売却するメリット

離婚において家を売却するメリットはいくつかあります。
1. 財産を公平に分配しやすくなる
離婚において家を売却するメリットのひとつは、財産を公平に分配しやすくなることです。
家を売却することで、売却代金が現金化され、これを元に財産を分割することが可能となります。この方法を選ぶことで、どちらの配偶者も公平なシェアを受け取ることができ、財産分与の際に争いや不公平感を減らすことができます。
2. 売却したお金は財産分与の対象になる
夫婦の共有財産を離婚時に均等に分割することを「清算的財産分与」といいます。売却しなければ家の分割はできないですが、売却し現金化することで、財産分与の対象として資産を均等に分けることが可能になります。
3. 売却で得たお金を住宅ローンの返済に充てられる
アンダーローン(売却金額が住宅ローンの残債よりも多い状態)であれば、売却したお金で一括返済できるため、売却ができます。離婚前に自宅を売却し、その売却代金で住宅ローンを完済すれば、ローンの名義や連帯保証契約について悩む必要もありません。そのため、売却益を夫婦双方で分け合うだけで財産分与が行え、手続きもスムーズに進むでしょう。
2.家を売却するタイミングは離婚前?離婚後?

家を売却するタイミングは離婚後が望ましいです。離婚前に不動産を売却し、その売却益を分け合う場合、贈与と見なされ、財産を受け取る側に贈与税がかかるリスクがあるからです。片方の名義のみで家を売却し、売却益を分配する際、贈与を受けたと解釈される可能性もあります。
離婚後に家を売却するメリットとして、売却活動に専念できるという点も挙げられます。すべての離婚手続きが終了し、新しい生活に向けての準備が整った状態で、売却活動に取り組めます。
一方で、売却が複数年にわたる場合、固定資産税の支払い義務が元所有者に発生するデメリットもあります。また、売却活動中は相手との連絡が必要となり、ストレスを感じることもあるでしょう。
一般的には、離婚後に不動産を売却することが多くのメリットをもたらすとされていますが、個々の状況や優先事項によって異なるため、慎重な検討と計画が必要です。
3.離婚で家を売却する時の手順

財産分与は、一般的に以下の流れで進めていきます。
1. 住宅ローンの残債、名義人、連帯保証人を確認する
離婚で家を売却する際の手順として、最初に行うべきことは、住宅ローンの残債、名義人、連帯保証人の確認です。
・住宅ローンの残債を確認する
まず、住宅ローンの残債を確認します。ローンの残り金額が家の現在の市場価格とどの程度一致しているかを把握することが重要です。住宅ローンの残債によっては、不動産を売却できない可能性もあります。金融機関に頼めば、住宅ローン残高の残高証明書を発行してくれますので、必ず調べておきましょう。
・名義人の確認をする
次に、家の名義人が誰であるかを確認します。夫婦のどちらか一方、または両方が名義人であるかに応じて、売却手続きの進め方が異なる場合があります。名義人の確認には以下の書類を使用します。
登記簿謄本…郵便やオンライン申請、窓口を通して誰でも法務局から取得できます。手数料は、郵便や窓口での取得時に600円、オンライン申請して窓口で受け取る場合は480円、郵送で受け取る場合は500円かかります。
不動産売買契約書…売買契約を結ぶ際に名義人が記名・押印した書類。通常、契約書は2通用意され、そのうちの1通は名義人が保管しています。
・連帯保証人の確認をする
住宅ローンに連帯保証人がいる場合、その保証人も関与しているため、売却に際して連帯保証人の同意や関与が必要になることがあります。
2. 家の価値を調べる
家がいくらで売れるのか調べます。家の価値を調べる方法はいくつかありますが、一番おすすめなのは、不動産会社に価値査定書の作成を依頼することです。この「無料査定」とも呼ばれる方法は、宅地建物取引業法に基づいて不動産の価値が算出されます。
鑑定会社に依頼すると数十万円の費用がかかりますが、不動産会社に依頼する場合、査定は無料です。その上、売却の仲介もそのまま依頼できるため、効率的に手続きが進められます。
3. アンダーローンかオーバーローンかを調べる
アンダーローン(売却金額が住宅ローンの残債を上回る状態)であれば、売却収益でローンを一括返済できるため、不動産の売却がスムーズに進みます。
一方、オーバーローン(売却価格が住宅ローンの残債を下回る状態)の場合、不動産を売却してもローンの残額が残ってしまいます。そのため、不足分のお金を自己資金で補わなければなりません。
住宅ローンの残債を一括返済できない場合、金融機関は抵当権を解除しません。抵当権が設定されたままの不動産を売買することは法律違反ではありませんが、抵当権付きの物件を買いたい人はほとんどいないでしょう。
したがって、住宅ローンの残債がある場合は、「アンダーローンである」または「完済するための自己資金がある」以外は、不動産の売却が難しいと言えます。
4. 財産分与の方法を決定し、公正証書を作成する
住宅ローンや名義の確認、家の価値を把握したら、不動産の分与方法を夫婦間で話し合います。
家を財産分与する方法は、以下の2つです。
1.売却して現金化し、分け合う
2.夫婦どちらかが家に住み続け、他方はその価値の半分を現金で受け取る
最終的には、夫婦間で合意した分与方法を公正証書として作成します。合意した分与方法は、公正証書としてまとめると安心です。公正証書とは、公証人が公的な権限で作成する公文書のこと。これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。
ただし、公正証書の作成には財産分与の金額に応じた手数料がかかります。日本公証人連合会が公表している費用は以下のとおりです。
財産分与の金額 | 公正証書の作成手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円~200万円 | 7,000円 |
200~500万円 | 11,000円 |
500~1,000万円 | 17,000円 |
1,000万~3,000万円 | 23,000円 |
出典:日本公証人連合会(12 手数料)
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12
コストはかかりますが、公正証書を作成することで、後からの問題を未然に防ぐことができます。
4.離婚で家を売る方法

離婚で家を売る際には、主に2つの方法があります。それは、仲介による売却と買取です。どちらの方法が最適かは、状況や優先事項によって異なります。迅速な売却を求める場合は買取が向いていますが、少しでも高値で売却したい場合は仲介による売却がおすすめです。それぞれのメリット・デメリットを考慮し、最適な方法を選んでください。
1.仲介
不動産会社が仲介に入って、家を売却します。
・仲介のメリット
市場価格に近い価格で売却できる可能性が高いです。より多くの買い手にアプローチでき、競争が生まれるため、高値で売却できるかもしれません。
・仲介のデメリット
売却までの時間がかかる場合があります。価格交渉や購入希望者とのやり取りも必要です。また、不動産会社への仲介手数料がかかることも考慮しなければなりません。
仲介を選択する場合、不動産会社と結ぶ媒介契約の種類についても知っておく必要があります。媒介契約には「専任媒介」「一般媒介」「専属専任媒介」の3つがあり、それぞれに特徴があります。
一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
依頼できる社数 | 複数可 | 1社のみ | 1社のみ |
自分で買主を見つける | 〇 | 〇 | × |
契約期間 | 自由 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
業務報告 | 売主から求められたら報告 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
一般媒介契約では、複数の不動産会社と契約できるため、営業活動の範囲を広げることができるというメリットがあります。間口を広げればそれだけ売却のチャンスが巡ってきそうですが、現実的には2、3社と契約するのが限度でしょう。
不動産会社が売主に対して行う業務報告も「2週間に1回以上」といった明確なルールはなく、売主から求められない限りは報告をする義務はありません。3つの媒介契約の中では一番縛りが弱めですね。
次に縛りが強いのは専任媒介契約と専属専任媒介です。1社としか媒介契約を結べないため、物件の囲い込み(他社に物件を紹介しないこと)が起こりやすい点や、販売戦略がない会社にあたってしまうと物件が売れにくいというリスクがあります。
しかし、専任媒介契約と一般媒介契約では、営業マンのモチベーションが異なるというのが実際のところです。一般媒介は、『営業活動を頑張っても他社で契約してしまうかも(つまり仲介手数料がもらえない)⇒積極的な営業活動を行わない』という不動産屋も少なくありません。
どの媒介契約がベストなのかは一概には言えませんが、それぞれの特徴をしっかりと理解して検討することをおすすめします。
2. 買取
不動産会社が直接家を買い取る方法です。仲介よりも価格は安くなりますが、売却までお急ぎの方には向いています。
・買取のメリット
迅速に売却できるのが最大のメリットです。売却にかかる手間や時間を省くことができます。
・買取のデメリット
市場価格よりも低い価格での売却になることが一般的です。すぐに売却できる分、利益は少なくなります。
5.まとめ
離婚に伴う財産分与の中でも、高額な不動産は特に慎重に扱わなければなりません。売却して現金化しない限り、不動産を「半分に分け合う」という方法は取れません。そのため、売却するか、どちらかが住み続けるか、名義をどうするかなど、お互いが納得できる形でしっかりと話し合いを進めましょう。
ミツバハウジングでは、離婚による売却や住み替えのご相談を随時承っております。住宅ローンの残債があって売却できるか不安という方もぜひ一度ご相談ください。
コラム・住まい探しに役立つ情報

買取再販住宅と中古住宅の違いやメリットデメリット
住宅メーカーや不動産会社などの事業者が住宅を買い取った後にリフォームまたはリノベーションを行い、中古物件として販売する住宅のことを「買取再販住宅」といいます。中古住宅と買取再販住宅、どちらがよいのか迷われている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回の記事では、買取再販住宅と中古住宅の違いや買取再販住宅のメリットデメリットについて詳しく解説します。
1.買取再販住宅と中古住宅の違い

買取再販住宅とは、住宅メーカーや不動産会社が住宅を買い取り、その後リフォームやリノベーションを施し、中古物件として再販することを指します。不動産業者が直接売主となるため、仲介手数料が発生しない点も特徴です。
中古住宅との違いは以下のようになります。
| 買取再販住宅 | 中古住宅 |
販売主体 | 住宅メーカーや不動産会社などの事業者が、住宅を買い取り、リフォームやリノベーションを行い、中古物件として販売します。 | 一般の個人が所有していた住宅であり、再販のために売り出されます。
|
改修やリノベーション | 買い取った後にリフォームやリノベーションが行われ、その費用は物件価格に含まれています。 | 改修やリノベーションの有無は、売主や物件によって異なります。必要な場合は購入者が負担することになります。 |
物件価格 | フォームやリノベーション費用を考慮しても、比較的安価に提供される傾向があります。 | 買取再販住宅よりも価格が幅広く、物件の状態やエリアによって大きく異なります。 |
仲介手数料 | 販売主体は不動産会社が直接売主となるため、仲介手数料は発生しません。 | 仲介業者が売買契約の仲介を行うため、仲介手数料が発生します。 |
保証 | 買取後の改修やリノベーションに関する一定期間の保証が提供されることがあります。 | 個人間の売買のため、保証が提供されることは一般的ではありません。 |
日本の空き家問題が深刻化する中、買取再販住宅は住宅市場の活性化に一役買っています。大手企業もこの分野に積極的に参入し、その中でも無印良品が展開する「MUJI× UR」は、無印良品とUR(都市再生機構)が連携した団地リノベーションプロジェクトとして注目を集めています。
2.買取再販市場は2030年に22%まで増加する見通し

大手企業も買取再販市場に参入する中、株式会社矢野経済研究所によると、今後も市場は拡大基調で推移し、2030年には2022年比で22.0%増の5万戸になると予測されています。
“不動産会社等が一旦購入し、リフォーム・リノベーションした後に販売する中古住宅買取再販は年々拡大しており、2022年の中古住宅買取再販市場規模(中古戸建及び中古マンションの買取再販戸数の合計)は成約戸数ベースで前年比5.1%増の41,000戸と推計した。市場拡大の主な要因は、中古住宅の需要増である。特に、新築分譲マンションの価格は高騰・高止まりしており、新築と比較して相対的に割安な中古住宅の需要が増えている。なかでも、買取再販物件は、リフォーム・リノベーションが施され、新築同様に入居できるため、人気を博している。”
引用元:株式会社矢野経済研究所
3.買取再販住宅の需要が高まる理由

古い住宅は時間とともに性能が低下し、老朽化が進む傾向にあります。そのため価格は比較的低めに抑えられますが、個人が購入する際にはリノベーションに関する判断や費用の見積もりが難しいという問題があります。
その問題をクリアしているのが買取再販住宅です。不動産会社などの事業者が提供する買取再販住宅は、豊富な経験に基づき、迅速かつ的確な判断が可能です。また、リノベーションに際しては市場の需要に合わせた間取りや設備仕様を取り入れることが一般的です。
一部の買取再販住宅は有名ブランドとのコラボレーションやデザイン性の高いリノベーションが施されています。ブランドのイメージや価値を反映したデザインや機能性が高く評価され、購入者の興味を引きつけます。このようなプロダクトに対するブランドの信頼や期待感が、需要の増加に寄与しているのでしょう。
また、仲介手数料が発生しない点や即入居可能な点も、買取再販住宅の魅力です。購入者にとっては手軽で明確な費用で新築並みのリノベーションが施された住宅が手に入るので需要が高まるのも納得ですね。
4.買取再販住宅のメリットデメリット

買取再販住宅のメリットデメリットをみてみましょう。
1. 買取再販住宅のメリット
買取再販住宅のメリットは多岐にわたりますが、以下に挙げることができます。
・新築並みのリノベーション済住宅に住める
買取再販住宅は、不動産会社や住宅メーカーなどの事業者が所有し、リフォームやリノベーションを施した物件が多いため、新築に近い状態で購入できます。
・即入居可能
リノベーションが完了した買取再販住宅は、すぐに入居することができます。新築や中古住宅の場合と比較して、引っ越しの手続きや待ち時間が短縮されます。
・価格が安い
通常、買取再販住宅の価格はリノベーションやリフォームを含めた総額で提示されます。そのため、購入者は費用の見積もりや追加費用の心配をする必要がありません。価格の透明性が高く、価格も比較的安く提供されているため、購入時の負担が軽減されます。
・仲介手数料がかからない
買取再販住宅の場合、売主が不動産会社や住宅メーカーであるため、仲介手数料が発生しません。
・選択肢が豊富
買取再販住宅にはさまざまなタイプやデザインの物件があります。また、有名ブランドとのコラボレーションやデザイン性の高いリノベーションが施された物件も存在します。自分の好みやニーズに合った物件を選ぶことができます。
・アフターサービスの利用がスムーズ
通常の中古住宅の売買では、契約不適合責任があるものの、それ以上のアフターサービスや保証がないことが一般的です。また、前の所有者にアフターサービスを求めることは難しいこともあります。一方、不動産会社が売主となる買取再販住宅では、買主は相談しやすい状況にあり、アフターサービスや保証を提供しているケースも多く見られます。(ただし、不動産会社ごとにアフターサービスや保証内容が異なるため、取引を検討している会社が提供するサービスを確認することが重要です)
・住宅ローン控除の適用期間が長い
詳しくは後述しますが、買取再販住宅は一般の中古住宅よりも住宅ローン控除の適用期間が長いというメリットもあります。買取再販物件は新築住宅と同様に住宅ローン控除の適用期間が13年となり、一般の中古住宅(適用期間10年)よりも適用期間が長めです。
2. 買取再販住宅のデメリットと注意点
買取再販住宅にはいくつかのデメリットや注意点があります。
・リノベーションの質にばらつきがある
買取再販住宅のリノベーションの質にはばらつきがあります。一部の物件では、安易なリノベーションや品質の低い材料が使用されている場合があるので注意しましょう。
・訳あり物件の可能性がある
過去に事件や事故が発生した経緯のある事故物件は、買い手がつきにくく価格が下がる傾向があります。不動産会社が事故物件を安価に仕入れ、リノベーションを施した後に買取再販住宅として販売するケースもあります。相場よりも過度に安い価格には注意が必要です。
・物件の不具合を見極めることが難しい
不動産会社によっては設計のプランニングは自社で行っても、施工は別業者に委託することもあります。その場合、最終的な仕上がりについて確認が不十分なことがあります。不安な場合は、ホームインスペクション(住宅診断)を利用するか、アフターサービスの保証を提供している業者を選ぶことが良いでしょう。
これらのデメリットや注意点を考慮しながら、買取再販住宅を検討することが賢明です。
5. 買取再販住宅を購入した場合の住宅ローン控除について

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して特定の住宅を購入、またはリフォームを行った場合に享受できる税制上の優遇制度です。年末時点での住宅ローン残高の0.7%に相当する額が一定期間内に所得税から控除されます。この控除が所得税で賄いきれない場合は、一部が住民税から控除されます。
住宅の種類 | 2023年入居 | 2024年入居 | 2025年入居 | |
新築住宅・買取再販 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 (子育て世帯・若者夫婦世帯向け5,000万円) | 2024年と同じ内容で検討中 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 (子育て世帯・若者夫婦世帯向け4,500万円) | 2024年と同じ内容で検討中 | |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 (子育て世帯・若者夫婦世帯向け4,000万円) | 2024年と同じ内容で検討中 | |
その他の住宅 (既存住宅「その他の住宅」の場合) | 3,000万円 | 0円 (2023年迄に新築の建築確認は2000万円) | 2024年と同じ内容で検討中 | |
既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 3,000万 | 3,000万 | 3,000万 |
その他の住宅 | 2,000万 | 2,000万 | 2,000万 | |
控除期間 | 新築住宅・買取再販 | 13年 (「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合10年) | 13年 (「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合10年) | 13年 (「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合10年) |
既存住宅 | 10年 | 10年 | 10年 |
※2024年3月現在の法令に基づいて作成
買取再販住宅と通常の中古住宅では、住宅ローン控除の条件に違いがあります。たとえば、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)省エネ住宅を購入し、令和4年から居住を始めた場合、買取再販住宅では借入限度額が4,500万円(子育て世帯や若者夫婦世帯の場合は5,000万円)となりますが、一般の中古住宅では3,000万円となります。また、控除期間にも3年の差があります。
これらの条件の違いから、買取再販住宅と通常の中古住宅での住宅ローン控除の適用が異なることがわかります。
6. まとめ
買取再販住宅は新築さながらの見た目と内装であるにもかかわらず、新築住宅に比べて安価である場合が多く、昨今の住宅市場において人気となっています。
買取再販住宅を検討する際には、記事内で解説したメリットやデメリット、注意点をしっかりと把握することが重要です。その上で、中古住宅の購入後にリフォームするなどの他の販売形態と比較し、自身のニーズや予算に合った住宅を選ぶことをおすすめします。
コラム・住まい探しに役立つ情報

任意売却のメリットデメリット-仲介や競売との違いは?
1.任意売却とは?

通常、不動産を担保とするローンは、融資時に抵当権を設定します。この抵当権はローンが完済されるまで消滅しません。また、他者の抵当権がついたままの物件は売却が難しいです。従って、物件を売却する際には、売却代金だけでなくローンの残債も完済しなければなりません。
しかし、このようなケースで役立つのが任意売却です。抵当権を持つ金融機関の同意を得れば、ローンの残債があるままでも物件を売却できるのです。
では、通常の売却(仲介)や競売とは何が違うのか?この章では、任意売却と仲介や競売との違いを説明します。
1.仲介との違い
通常の売却では、不動産の所有者である売主が主体となります。不動産会社を介した媒介契約による売却や、自ら買主を見つける自己発見取引が一般的です。
住宅ローンや他の債務の返済に遅れがなく、不動産の売却代金で残債を一括返済できる場合、通常の売却が選択肢となります。
売却価格の目安は、市場価格や不動産会社の査定額に近い金額です。また、売却を決断した場合でも、理想の価格での買主が見つからないなどの理由で売却を取りやめることが可能です。
2.競売との違い
住宅ローンの支払いが数ヵ月延滞すると、抵当権の設定された物件は競売にかけられます。競売は、住宅ローンやその他の借金の返済が遅れ、債権者が競売手続きを開始し、裁判所がその正当性を認めた場合に行われる売却方法です。
競売では、売主としての主体は不動産の所有者ではなく、債権者の申立てを認めた裁判所が主体となります。買主が見つかれば、所有者の意思に関係なく物件が強制的に売却されます。
売却価格の目安は仲介や任意売却よりも低く、5~7割程度とされます。また、競売された後も残債があれば、返済は継続されます。
3.仲介・任意売却・競売 それぞれの違い
それぞれの違いを以下にまとめましたので、参考にしてください。
| 仲介 | 任意売却 | 競売 | |
| 売主 | 不動産の所有者 | 不動産の所有者 | 裁判所 |
| 返済状況 | 返済の遅延がない | 返済が遅延しており、または今後の返済が難しいと判断されている | 返済遅延後、督促の期間内に返済できなかった |
| 利用できる条件 | 売却したお金で残債を一括返済できる | 債権者の承認が必要。任意売却が開始されたら、債務者の意思だけでは取り消せない | 債権者が競売を申し立て、裁判所が承認した場合。債務者が競売を取り消すことはできない |
| 売却価格 | 市場価格と同程度 | 市場価格の8~9割 | 市場価格の5~7割 |
| 価格決定権 | 不動産の所有者 | 金融機関と協議 | 裁判所 |
| 仲介手数料 | あり | あり | なし |
2.任意売却のメリット5つ

次に、任意売却のメリットを解説します。
1.競売よりも高く売れる
競売で不動産を売却する場合、通常の市場相場よりも大幅に低い価格になることが一般的です。一般的には、市場価格の5割から7割程度になることが多いです。
この価格の低さは、いくつかの理由によるものです。まず、買主が物件を購入する前に内覧することが難しい場合があります。また、競売物件の情報が公開されてから入札が開始されるまでの時間が短いため、買主が情報を入手し、準備を整える時間が限られています。さらに、現所有者が立ち退きを拒否する場合、買主は自ら交渉しなければならないこともあります。
このような理由から、競売では物件が安い価格で売却される傾向があります。一方、任意売却では通常の不動産の売買と同様に、不動産会社の仲介を通じて物件が売却されます。そのため、市場相場と同等の価格で売却されることが一般的です。
2.住宅ローンの残債を分割返済できる
通常の売却では、住宅ローンの残債を一括返済しなければ、金融機関は抵当権を解除してくれません。しかし、金融機関は任意売却を行う人に対して、一括返済を求めることは無謀というのも理解しています。
そのため、返済が滞る状況を防ぐために、金融機関は返済額を適切に設定し、分割返済を可能にすることもあります。
ただし、滞納が続いた場合、金融機関は「住宅ローンを返済する意思がない」と判断し、一括返済を求めることがあります。督促の連絡が何度も無視されたり、対応されなかったりした場合、競売の対象となる可能性があることに注意が必要です。
3.売却費用を抑えられる可能性がある
任意売却では、債権者の同意を得て、売却代金の一部を経費や清算費用に充てることができる場合があります。
物件の任意売却を検討する人々は、通常現金が十分でないことが多いです。引っ越し費用や税金の支払いなど、必要な支出をまかなえないこともよくあります。任意売却では、債権者の同意を得て、売却代金の一部をこれらの費用に充てることができる場合があります。
一方、競売では売却代金は裁判所に管理され、全額が債権者に支払われます。引っ越しやその他の必要な出費がある場合、自分で資金を用意する必要があります。
4.引き渡し日を調整できる
競売では、強制退去日が定められ、その日までに物件を退去する必要があります。一方、任意売却では、売主や金融機関との交渉によって、より柔軟な引き渡し日を設定することが可能です。これにより、売主や買主の都合に合わせて引き渡し日を調整することができます。
5.近隣住民に知らずに売却できる
競売では、裁判所の競売情報などを通じて売主の情報が公開されますが、任意売却では不動産会社と相談して広告公開範囲を決定できます。
そのため、売主はプライバシーを守りつつ物件を売却できます。特定の条件下でのみ物件情報を公開することも可能であり、近隣住民に知られずに売却を進めることができます。
3. 任意売却のデメリット5つ

続いて、任意売却のデメリットです。
1.ブラックリスト(信用情報)に載る
競売でも同様ですが、任意売却が必要な場合、信用情報機関に事故情報が記載され、いわゆるブラックリスト入りとなります。
個人信用情報に情報が登録されるタイミングは金融機関や信用情報機関によって異なりますが、一般的にはローンを3回滞納したタイミングで登録されます。この情報が登録されると、5年間は新たなローンの借り入れが難しくなります。さらに、クレジットカードの審査にも影響を与え、普段の生活にも支障が出る可能性があります。
ブラックリスト入りすると、数年間は新たな借り入れやクレジットカードの取得が制限されますので、任意売却によって信用情報に傷がつかないという保証はありません。
2.『任意売却=残債がゼロになる』わけではない
任意売却を行った場合でも、すべての残債が消えるわけではありません。売却代金が残債を十分にカバーしない場合、残債が残る可能性があります。そのため、売却後に返済すべき残債が残ることになります。
ただし、任意売却の場合は一括返済だけでなく、分割返済が可能なケースもあります。具体的に返済すべき額は、収入状況などを考慮して金融機関が決定しますが、一般的には月額5,000円から30,000円程度で設定されることが一般的です。
3. 期限内までに売却しなければならない
通常の不動産売却とは異なり、任意売却には売却期限が設定されます。
この期限は、競売手続きと同時に進められます。具体的には、競売の開札期日の前日までに、代金の受け取りと物件の引き渡しが完了する必要があります。買主との交渉も必要なため、スケジュールを十分に確保することが重要です。
4.金融機関の同意を得られないと売却できない
任意売却は、個人の裁量では自由に行うことができません。任意売却の可否は金融機関によって決定され、一度任意売却の手続きを始めると取り消すことはできません。また、場合によっては、購入希望者が現れたのにも関わらず金融機関からの承諾を得られないケースも考えられます。例えば、物件の査定額が残債を極端に下回る場合、返済計画が現実的でなければ任意売却することができない可能性があります。
5.任意売却するには債権者の同意が必要
任意売却を進める際には、連帯保証人や共有名義人の同意が必要になります。
しかし、任意売却を望んでも、名義人の許可を得られない場合もあります。たとえば、離婚後に元夫名義の家に元妻が居続ける場合、元夫が住宅ローンの支払いを滞納し、金融機関からの督促を無視し続ける
4. 任意売却を検討した方がよいケース

ここまで任意売却のメリットデメリットを解説してきましたが、実際に任意売却を検討した方がよいのはどのようなケースなのかみてみましょう
1.金融機関から督促状や催告状が届いた場合
住宅ローンの返済が滞ると、金融機関から督促状や催告状が届くことがあります。この時は任意売却を視野に入れる必要があります。
督促状にある返済期限までに返済が完了した場合は大きな問題はありませんが、今後も遅延が続く可能性がある場合は、住宅ローンを提供している金融機関との返済の相談や、競売になる前に任意売却の準備を始めることが賢明です。
ただし、物件が実際に売れるまでには3ヵ月から6ヵ月かかることが一般的ですので、できるだけ早く行動を開始することが重要です。
2.売却後に残債を一括返済できない場合
売却代金と「自己資金」だけでは一括返済が難しい場合は、通常の売却ではなく任意売却を選択することも一つの手段です。
この「自己資金」には親族からの援助や他の金融機関からの借り入れで得た資金も含まれます。それらの資金があってもなお完済できないというケースです。
不動産会社の査定額から売却にかかる諸経費を差し引き、その金額と自己資金を合わせて残債を完済できるかどうかを検討しましょう。
6. まとめ
任意売却できるのは競売の開札日前日までです。競売の開札日は、返済の滞納から数えておよそ8ヵ月後。督促後の任意売却への期間は非常に短いため、迅速な行動が成功の鍵となります。
売却でお悩みの方は、ミツバハウジングまでご相談ください。任意売却、仲介や買取での売却、お客様にとってベストな方法をお探しします。お電話でもメールでも構いません。おひとりで悩まず、まずはお問い合わせください。
コラム・住まい探しに役立つ情報

『住みたい街ランキング2024』横浜駅が7年連続の1位!埼玉県の大宮駅は2位にランクイン
◎中古住宅買取再販市場は2030年に22%増の5万戸へ。市場拡大の理由とは?買取再販物件の購入ポイントも解説!
https://suumo.jp/journal/2023/10/18/198482/
◎ランキングの補足
https://suumo.jp/journal/2024/02/28/201057/
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/data/sumimachi2024syutoken_eki/
株式会社リクルートが毎年発表している『住みたい街ランキング』
2024年はどのような順位になったのかというと、横浜駅が7年連続で1位!そして、ランキング上位常連である吉祥寺を抑えて大宮駅が2位となりました。
横浜駅も大宮駅も、駅として便利なのは分かるけれど、「住みたい街」として選ばれるのはなぜ?と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
横浜駅にいたっては、なぜ7年連続1位を獲得するほど人気なのか?大宮駅は、都心の駅よりどのような点が魅力的なのか?あくまでも考察にはなりますが、いくつかピックアップしてみたいと思います。
1.2024年『住みたい街ランキング』の結果

それでは、ランキングの結果からみていきましょう。
1. 1位は横浜駅、2位は吉祥寺を抜いて大宮がランクイン
冒頭でも説明したとおり、今年は横浜駅が7年連続で1位、2位は大宮駅となりました。1位から10位までのランキングを以下にまとめましたので、ご覧ください。
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 駅名(代表的な路線) | 2024年得点 |
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 横浜(JR京浜東北線) | 1683 |
2位 | 3位 | 3位 | 4位 | 4位 | 4位 | 9位 | 大宮(JR京浜東北線) | 1054 |
3位 | 2位 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 吉祥寺(JR中央線) | 996 |
4位 | 4位 | 4位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 恵比寿(JR山手線) | 952 |
5位 | 5位 | 7位 | 7位 | 7位 | 5位 | 7位 | 新宿(JR山手線) | 777 |
6位 | 6位 | 6位 | 5位 | 5位 | 7位 | 8位 | 目黒(JR山手線) | 690 |
7位 | 7位 | 9位 | 9位 | 8位 | 11位 | 5位 | 池袋(JR山手線) | 666 |
8位 | 11位 | 8位 | 6位 | 6位 | 6位 | 4位 | 品川(JR山手線) | 634 |
9位 | 9位 | 13位 | 13位 | 12位 | 15位 | 16位 | 東京(JR山手線) | 619 |
10位 | 12位 | 5位 | 8位 | 10位 | 8位 | 10位 | 浦和(JR京浜東北線) | 602 |
引用:株式会社リクルート「SUUMO住みたい街ランキング2024 首都圏版」より編集
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20240228_housing_01.pdf
右端の「2024年得点」ですが、これは「あなたが、今後住んでみたいと思う街(駅)はどこですか」という問いに対して、回答によって以下のように点数を分けられています。
・最も住んでみたい街(駅)…3点
・2番目に住んでみたい街(駅)… 2点
・3番目に住んでみたい街(駅)… 1点
横浜駅の7年連続1位はさすがとしか言いようがないですね!
ちなみに、この調査では、「横浜駅を中心とした半径2キロ圏内」が横浜駅とされています。その理由は、横浜駅周辺のほとんどが商業施設やオフィスであり、住宅は希少だからです。そのため、みなとみらい21地区(中央地区・新港地区・横浜駅東口地区の総称)も含め、「横浜駅」として捉えられています。横浜駅から半径2キロ圏内のみなとみらい21地区ですと、横浜駅東口地区が該当します。
大宮駅に関しては、過去最高の2位です。過去の推移をみてみると、2018年は9位で5位以内にもランクインしていませんでしたが、その後、4位、3位と年々上昇し、2024年は長らく人気だった吉祥寺を抑えて2位になりました。このようなランキングでは、都心が上位に入ることが多いため、大宮駅が2位という結果に驚かれた方も多いかもしれませんね。
2. 11位以降はランキングの入れ替えが激しい
続いて、11位以降のランキングもみてみましょう。
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 駅名(代表的な路線) | 2024年得点 |
11位 | 9位 | 11位 | 11位 | 11位 | 13位 | 11位 | 渋谷(JR山手線) | 568 |
12位 | 8位 | 10位 | 12位 | 13位 | 10位 | 14位 | 鎌倉(JR横須賀線) | 556 |
13位 | 13位 | 12位 | 10位 | 9位 | 12位 | 11位 | 中目黒(東急東横線) | 552 |
14位 | 14位 | 14位 | 14位 | 20位 | 9位 | 6位 | 武蔵小杉(東急東横線) | 506 |
15位 | 16位 | 16位 | 39位 | 49位 | 41位 | 46位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 503 |
16位 | 17位 | 22位 | 19位 | 36位 | 22位 | 30位 | 舞浜(JR京葉線) | 482 |
17位 | 18位 | 15位 | 22位 | 21位 | 24位 | 18位 | 船橋(JR総武線) | 469 |
18位 | 21位 | 19位 | 18位 | 14位 | 14位 | 15位 | 中野(JR中央線) | 443 |
19位 | 20位 | 24位 | 20位 | 32位 | 34位 | 27位 | 桜木町(JR根岸線) | 431 |
20位 | 15位 | 18位 | 16位 | 15位 | 20位 | 25位 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 418 |
21位 | 22位 | 17位 | 15位 | 19位 | 23位 | 29位 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 409 |
22位 | 19位 | 23位 | 25位 | 23位 | 18位 | 22位 | 立川(JR中央線) | 407 |
23位 | 28位 | 20位 | 28位 | 22位 | 20位 | 23位 | 北千住(東京メトロ千代田線) | 404 |
24位 | 26位 | 36位 | 31位 | 38位 | 44位 | 43位 | みなとみらい(みなとみらい線) | 373 |
25位 | 25位 | 21位 | 23位 | 25位 | 26位 | 21位 | 柏(JR常磐線) | 371 |
引用:株式会社リクルート「SUUMO住みたい街ランキング2024 首都圏版」より編集
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20240228_housing_01.pdf
横浜市内のエリアでいうと、桜木町駅とみなとみらい駅が過去最高の順位を記録しています。みなとみらい駅にいたっては2018年の43位からじわじわと順を伸ばし、2023年には26位、そして今回のランキングでは24位にまで上昇しました。もともと、みなとみらい駅は観光地として人気がありましたが、居住するイメージがしづらいエリアでした。しかし、近年ではみなとみらい21地区の開発が進み、高層マンションの建設や生活に必要な買い物施設などが増えて、居住エリアとしても注目が集まるようになったのでしょう。
次に注目していただきたいのは21位のさいたま新都心駅です。さいたま新都心駅は、再開発で新しく作られた駅で、2位の大宮駅の隣にあります。
JR京浜東北・根岸線、高崎線、東北本線の3路線が走っており、上野東京ラインを利用すれば、乗り換えなしの30分程度で東京駅へ着きます。さらに、隣駅の大宮駅から新幹線を利用することもできるので、その交通利便性の良さに人気があるようです。
2.横浜駅が7年連続1位に!人気の理由は?

横浜駅が住みたい街として7年連続1位を獲得するほど人気の理由をいくつかピックアップしてみました。
1. 10路線あるので多方面にアクセスしやすい
横浜駅は、なんと10路線が乗り入れています。JR東海道本線やJR京浜東北線、そして横浜市営地下鉄ブルーラインなど、多彩な路線が利用できます。
【横浜駅から利用できる路線】
JR京浜東北線
JR東海道本線(上野東京ライン)
JR横須賀線
JR根岸線
JR湘南新宿ライン
東急東横線
相模鉄道本線
横浜高速鉄道みなとみらい線
横浜市営地下鉄ブルーライン
京急本線
たとえば、横浜から東京の渋谷や新宿まで、乗り換えなしの30分以内でアクセス可能です。さらに、大宮や宇都宮、前橋、千葉など、関東圏の主要地域へも乗り換えなしで行くことができます。
2. 商業施設や飲食店が豊富
横浜駅周辺には、多種多様な商業施設や飲食店が集まっています。
【横浜駅西口から徒歩10分圏内にある商業施設】
・横浜高島屋
・横浜ポルタ
・JR横浜タワー(NEWoMan横浜)
・相鉄ジョイナス
・横浜ビブレ
・横浜モアーズ
・CeeU Yokohama(イオンモール)
【横浜駅東口から徒歩10分圏内にある商業施設】
・そごう横浜店
・マルイシティ横浜
・ルミネ横浜
・横浜ベイクォーター
横浜駅周辺には、ショッピングモールや百貨店、カフェやレストラン、居酒屋など、幅広いジャンルの施設が揃っています。横浜駅に住んでいて、買い物や食事に困ることはまずないでしょう。
3. 病院や学校、保育園の数も多い
横浜駅周辺には、多くの病院や医療施設が立地しています。また、学校や保育園も数多くあり、子育て世帯にとって安心できる環境が整っています。
これらの施設が充実していることで、住民の健康や教育に対するアクセスが良好であり、生活の利便性が高いと評価されています。
4. 自然を感じられるスポットもある
横浜駅周辺は都会的なイメージが強いですが、実は自然を感じられる公園も点在しています。
たとえば、横浜駅西口から徒歩10分の場所にある「沢渡中央公園」は、遊具はありませんが、地元の方に親しまれているお散歩コースとして知られています。
さらに、徒歩約15分の位置にある「高島水際線公園」では、隣に流れる帷子川の景色を眺めながら心地よい散歩を楽しむことができます。
これらの公園は、休日にリフレッシュしたり散策を楽しんだりするのに最適な場所です。また、子どもたちも安全に遊べる環境が整っています。
3.2位の大宮駅は埼玉県内のターミナル駅

大宮駅は、1885年(明治18年)に開業した「大宮」駅は、現在、JRと私鉄を合わせて14の路線が乗り入れる埼玉県内最大のターミナル駅。「住みたい街」として人気の理由をみてみましょう。
1. 大宮駅が人気の理由は交通利便性の高さ
大宮駅は、JR京浜東北線、埼京線、武蔵野線、湘南新宿ライン、東武野田線などの在来線をはじめ、東北新幹線や上越新幹線など14路線が利用できます。
【在来線】
・JR宇都宮線(東北本線)
・JR高崎線
・JR宇都宮線・高崎線(上野東京ライン)
・JR埼京線
・JR川越線
・JR湘南新宿ライン
・JR京浜東北・根岸線
【私鉄】
・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)
・東武野田線(アーバンパークライン)
【新幹線】
・JR東北・北海道新幹線
・JR秋田新幹線
・JR山形新幹線
・JR上越新幹線
・JR北陸新幹線
JR東日本の調査によると、大宮駅の乗車数は平均約25.8万人で、JR東日本の中でも、大宮駅の1日の乗車人員は8番目に多く、朝夕の通勤時間はかなり混雑します。
新幹線も利用できるので、出張が多い方や旅行が好きな方にもおすすめの駅です。
2. 商業施設が多いので都心に行く必要がない
大宮駅には多くの路線が通るため、駅構内は広大なスペースになっています。駅弁の販売や商業施設エキュートとの直結など、改札を出ずとも買い物ができる特長があります。
娯楽や買い物に関しては、大宮駅前には大規模な施設が集中しています。東口には「ルミネ大宮店」「高島屋大宮店」、西口には「そごう大宮店(ビックカメラを併設)」「大宮アルシェ」「大宮駅西口DOMショッピングセンター(丸井、東急ハンズなど)」「大宮ソニックシティ」などがあります。
食品からファッション、雑貨、書籍まで、著名なテナントが多数揃っており、全てを一日で回るのは困難なほど多岐にわたります。このような商業施設の充実ぶりから、都心へ行く必要がないと感じる人も多いでしょう。
3. 子育て支援が手厚い
大宮駅があるさいたま市は、子育てがしやすい環境が整っており、その理由の一つには、0歳から中学校卒業までの子どもを対象とした嬉しい制度があります。
通院や入院にかかる医療費と入院時の食事負担額の半分が助成される制度や、子どもが3人以上の家庭には5万円分の「3キュー子育てチケット」が配布され、ベビーシッター代やおむつ購入費に充てることができます。
さらに、大宮駅周辺には医療施設が充実しています。産婦人科や小児科、耳鼻科などが数多くあり、安心して子育てをすることができます。
4.横浜市内で家を買うなら戸塚エリア、埼玉県内なら川口や蕨もおすすめ

「住みたい街ランキング」の上位に入る駅の特徴として大きなポイントとなるのは、利便性が高いこと。横浜駅にしても大宮駅にしても、複数の路線が利用できて、駅周辺に商業施設などが充実しているエリアです。ひと昔前なら「落ち着いた住環境」を望んでいた方が多かったのですが、近年人気があるのは利便性の高さ。そのため、ターミナル駅にある物件は人気が集まります。
しかし、ターミナル駅にある物件が便利なのは理解していても、住むには落ち着かない…という方が多いと思います。そこで、おすすめなのはターミナル駅から少しずらして家を買うことです。
たとえば、埼玉県の南部で見ると、比較的落ち着いた環境なのは蕨市です。南部の中で物件価格が比較的安い傾向にあるのも蕨市となります。価格が安いから交通アクセス悪いわけでもなく、蕨市にある蕨駅から快速を利用すれば、東京駅まで約31分、品川駅まで約41分で着きます。
横浜市でいうなら、戸塚エリアも人気が出てきています。たとえば、戸塚駅を例に挙げると、横浜駅までJR東海道線で約10分、湘南新宿ラインで新宿駅、渋谷駅、池袋駅も乗り換えなしでアクセスできます。再開発によって駅周辺にも商業施設も建てられ、買い物にも困りません。再開発が進んでいる一方で、駅から少し離れると閑静な住宅街が広がる点も戸塚エリアの特徴で、新築も中古も物件数が豊富にあります。物件数でいえば、横浜駅周辺よりも戸塚エリアのような住宅街がある駅の方が選択肢は豊富です。
蕨駅や戸塚駅を例に挙げましたが、これらはあくまでも一例で、他のエリアにもおすすめの家はたくさんあります。ランキング下位のエリアにも良い物件は必ずあります。家を購入する際は、できるだけ視野を広げて探してみましょう。
5.まとめ
ランキング1位の横浜駅や2位の大宮駅、どちらも利便性が高くて素晴らしいエリアです。ただ、家探しはランキングにこだわらず、「自分が住みやすい街」や「予算内で買える家」を選ぶことが重要です。
横浜市内や埼玉県の家をお探しならミツバハウジングまでご相談ください。
「今すぐ買う予定はないけれど、とりあえず相談だけしたい」という方も大歓迎です!メールでもお電話でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
ミツバハウジング さいたま 蕨支店
埼玉県川口市・蕨市を中心に県内全域の不動産をお取り扱いしています。
https://www.mitsuba-h.com/saitama/
横浜でマイホームをお探しの方はこちらの本店にて承っております。横浜市戸塚区・泉区を中心に県内全区域の不動産をお取り扱いしています。
ミツバハウジング 東戸塚 本店
コラム・住まい探しに役立つ情報

『リノベ済物件』or『買ってからリノベ』
『リノベ済物件』を買うか『買ってからリノベ』するか、どちらが賢い選択なのか。
中古物件を検討されている方は、このふたつの選択肢に直面します。
この記事では、それぞれの特徴や注意点を探り、最適な選択を見つけるためのポイントを解説します。
1.リノベとリフォームの違い

リノベーションとリフォームは、両方とも建物や住宅を改修することを指しますが、微妙な違いがあります。
・リノベーション
リノベーションは、建物や住宅の性能や価値を向上させることを目的とし、部分的または全体的な改造を行います。つまり、建物や住宅の構造を変更し、新しいデザインや機能を追加することを指します。リノベーションはリフォームよりも工事の規模が大きく、部分的な修繕だけでなく、大規模な改修も行われることがあります。
・リフォーム
リフォームは主に「古くなった部分を新品同様の状態に戻す」ことを目的として行われます。具体的には、お風呂やトイレ、キッチンなどの設備を新品と交換する工事や、壁紙やフローリングを張り替えるなどが該当します。リフォームは主に部分的な修繕を行い、間取りや内装の変更は行いません。
簡潔に言えば、リフォームは古いものを新しい状態に戻すことを重視し、リノベーションは新しいデザインや機能を追加することを目的としています。
2.リノベ物件の買い方は2パターン

リノベ物件の買い方は主に2つ。リノベ済物件を購入するか、中古物件を購入してからリノベするか。それぞれの特徴をみていきましょう。
1.『リノベ済物件』を購入する
リノベ済物件を購入する場合は、すぐに快適な生活を始めたい方やリスクを避けたい方、リノベーションの内容に強いこだわりがない方に適しています。
この方法のメリットデメリットは以下のとおりです。
【メリット】
・即入居できる
リノベーションが完了しているため、すぐに入居することができます。手間や時間をかけずに新しい住居で生活を始めることができます。
・手間や時間がかからない
リノベーションの工程やコストを自分で管理する必要がないため、リスクが軽減されます。予期せぬトラブルや追加費用の心配が少なくなります。
・価格が明確なので資産計画を立てやすい
物件価格にはリノベ費用も含まれているため、資金計画が立てやすいというメリットもあります。追加費用が発生することはほとんどないので建売住宅などの完成物件を購入する感覚と同じです。
【デメリット】
・価格が高い
リノベーションが施された物件は一般に価格が高めに設定されていますが、手間や時間の節約を考慮するとコストパフォーマンスは高いと言えます。
・シンプルなデザインが多い
リノベーションにはさまざまなスタイルがありますが、リノベ済物件は万人受けしやすいシンプルなデザインであることが多いです。個性的なリノベを求める方には物足りないかもしれません。
2.『買ってからリノベ』する
中古物件を購入してからリノベをする方法です。中古物件購入、リノベーション、住宅ローン、この3つをこなしていかなくてはならないため、プロセスが多いですが、時間や手間をかけてでも理想の家づくりをしたい方には適しています。
この方法のメリットデメリットは以下のとおりです。
【メリット】
・自由度が高い
中古住宅を購入し、その後のリノベーションによって、自分の好みやニーズに合った家を実現できます。
・家づくりのプロセスが見える
リノベーションの工程やデザインに参加できるため、家づくりのプロセスを楽しむことができます。
【デメリット】
・予期せぬ問題が発生するリスクがある
中古物件を購入しリノベーションする場合、予期せぬ問題が発生するリスクがあります。建物の構造や設備の劣化、補修や改修が必要な箇所などに対処する必要があります。
・すぐに入居できない
中古物件のリノベーションには時間がかかる場合があります。設計や工事の準備、実際の工事、そして引っ越し準備など、複数の段階を経るため、入居までの期間が長くなる可能性があります。
・手間や時間がかかる
物件購入とリノベーションを別々の会社に依頼したい場合、注文住宅なみに手間がかかります。なぜなら、物件探し、リノベーション、住宅ローン、この3つをこなしていかなくてはならないからです。大変な思いをしたからこそ、自分好みの家を手にした達成感はあるかと思いますので、デメリットとも言い難いですが、家づくりに手間をかけたくない方には負担になるでしょう。
3. 『リノベ済物件』選びのチェックポイント

リノベ済み物件を選ぶ際には、注意深く検討する必要があります。以下は、その際に重要なチェックポイントです。
1.工事範囲の確認
リノベーションがどの部分に行われたかを確認します。内装の美観だけでなく、配管や電気設備、構造的な改修も重要です。物件が本当に必要とするリノベーションが行われているかを確かめましょう。
2.物件価格の適正さ
物件価格にリノベーション費用が適切に反映されているかを確認します。『リノベ済物件』の中には、過剰な価格設定が見られることもあります。そのため、提示価格を鵜呑みにせずに、相場に合っているかどうかを必ず確認することが重要です。中古住宅の価格相場を知りたい方には、国土交通省が運営している「不動産取引価格情報検索」をご利用いただくことをおすすめします
3.法令遵守の確認
時折、違法に増築されたり、建築基準法などの法令に違反されたりしている中古住宅が市場に出回ることがあります。一般的な違反事項としては、建蔽率や容積率の超過が挙げられます。たとえデザインが気に入っても、このような物件の購入はおすすめできません。そもそも、違法建築は住宅ローンが通らない可能性があります。
4. 『買ってからリノベ』する時の注意点
![{"type":"elementor","siteurl":"https://www.mitsuba-h.com/wp-json/","elements":[{"id":"b1e5cfe","elType":"widget","isInner":false,"isLocked":false,"settings":{"image":{"url":"https://www.mitsuba-h.com/wp-content/uploads/2024/05/コラム家が売れなかった場合の選択肢_4.jpg","id":11728,"size":"","alt":"コラム家が売れなかった場合の選択肢_4","source":"library"},"image_size":"full","image_custom_dimension":{"width":"","height":""},"caption_source":"none","caption":"","link_to":"none","link":{"url":"","is_external":"","nofollow":"","custom_attributes":""},"open_lightbox":"default","align":"","align_tablet":"","align_mobile":"","width":{"unit":"%","size":"","sizes":[]},"width_tablet":{"unit":"%","size":"","sizes":[]},"width_mobile":{"unit":"%","size":"","sizes":[]},"space":{"unit":"%","size":"","sizes":[]},"space_tablet":{"unit":"%","size":"","sizes":[]},"space_mobile":{"unit":"%","size":"","sizes":[]},"height":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"height_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"height_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"object-fit":"","object-fit_tablet":"","object-fit_mobile":"","object-position":"center center","object-position_tablet":"","object-position_mobile":"","opacity":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"css_filters_css_filter":"","css_filters_blur":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"css_filters_brightness":{"unit":"px","size":100,"sizes":[]},"css_filters_contrast":{"unit":"px","size":100,"sizes":[]},"css_filters_saturate":{"unit":"px","size":100,"sizes":[]},"css_filters_hue":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"opacity_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"css_filters_hover_css_filter":"","css_filters_hover_blur":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"css_filters_hover_brightness":{"unit":"px","size":100,"sizes":[]},"css_filters_hover_contrast":{"unit":"px","size":100,"sizes":[]},"css_filters_hover_saturate":{"unit":"px","size":100,"sizes":[]},"css_filters_hover_hue":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"background_hover_transition":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"hover_animation":"","image_border_border":"","image_border_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"image_border_width_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"image_border_width_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"image_border_color":"","image_border_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"image_border_radius_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"image_border_radius_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"image_box_shadow_box_shadow_type":"","image_box_shadow_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"caption_align":"","caption_align_tablet":"","caption_align_mobile":"","text_color":"","caption_background_color":"","caption_typography_typography":"","caption_typography_font_family":"","caption_typography_font_size":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"caption_typography_font_size_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"caption_typography_font_size_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"caption_typography_font_weight":"","caption_typography_text_transform":"","caption_typography_font_style":"","caption_typography_text_decoration":"","caption_typography_line_height":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"caption_typography_line_height_tablet":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"caption_typography_line_height_mobile":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"caption_typography_letter_spacing":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"caption_typography_letter_spacing_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"caption_typography_letter_spacing_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"caption_typography_word_spacing":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"caption_typography_word_spacing_tablet":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"caption_typography_word_spacing_mobile":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"caption_text_shadow_text_shadow_type":"","caption_text_shadow_text_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"color":"rgba(0,0,0,0.3)"},"caption_space":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"caption_space_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"caption_space_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_title":"","_margin":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_element_width":"","_element_width_tablet":"","_element_width_mobile":"","_element_custom_width":{"unit":"%","size":"","sizes":[]},"_element_custom_width_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_element_custom_width_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_element_vertical_align":"","_element_vertical_align_tablet":"","_element_vertical_align_mobile":"","_position":"","_offset_orientation_h":"start","_offset_x":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_offset_x_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_x_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_x_end":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_offset_x_end_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_x_end_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_orientation_v":"start","_offset_y":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_offset_y_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_y_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_y_end":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_offset_y_end_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_offset_y_end_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_z_index":"","_z_index_tablet":"","_z_index_mobile":"","_element_id":"","_css_classes":"","_animation":"","_animation_tablet":"","_animation_mobile":"","animation_duration":"","_animation_delay":"","_transform_rotate_popover":"","_transform_rotateZ_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateZ_effect_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateZ_effect_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotate_3d":"","_transform_rotateX_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateX_effect_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateX_effect_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateY_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateY_effect_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateY_effect_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_perspective_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_perspective_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_perspective_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translate_popover":"","_transform_translateX_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateX_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateX_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateY_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateY_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateY_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_popover":"","_transform_keep_proportions":"yes","_transform_scale_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleX_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleX_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleX_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleY_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleY_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleY_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_skew_popover":"","_transform_skewX_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_skewX_effect_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_skewX_effect_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_skewY_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_skewY_effect_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_skewY_effect_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_flipX_effect":"","_transform_flipY_effect":"","_transform_rotate_popover_hover":"","_transform_rotateZ_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateZ_effect_hover_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateZ_effect_hover_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotate_3d_hover":"","_transform_rotateX_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateX_effect_hover_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateX_effect_hover_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateY_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateY_effect_hover_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_rotateY_effect_hover_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_perspective_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_perspective_effect_hover_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_perspective_effect_hover_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translate_popover_hover":"","_transform_translateX_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateX_effect_hover_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateX_effect_hover_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateY_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateY_effect_hover_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_translateY_effect_hover_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_popover_hover":"","_transform_keep_proportions_hover":"yes","_transform_scale_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_hover_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_hover_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleX_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleX_effect_hover_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleX_effect_hover_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleY_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleY_effect_hover_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scaleY_effect_hover_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_skew_popover_hover":"","_transform_skewX_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_skewX_effect_hover_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_skewX_effect_hover_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_skewY_effect_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_skewY_effect_hover_tablet":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_skewY_effect_hover_mobile":{"unit":"deg","size":"","sizes":[]},"_transform_flipX_effect_hover":"","_transform_flipY_effect_hover":"","_transform_transition_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"motion_fx_transform_x_anchor_point":"","motion_fx_transform_x_anchor_point_tablet":"","motion_fx_transform_x_anchor_point_mobile":"","motion_fx_transform_y_anchor_point":"","motion_fx_transform_y_anchor_point_tablet":"","motion_fx_transform_y_anchor_point_mobile":"","_background_background":"","_background_color":"","_background_color_stop":{"unit":"%","size":0,"sizes":[]},"_background_color_stop_tablet":{"unit":"%"},"_background_color_stop_mobile":{"unit":"%"},"_background_color_b":"#f2295b","_background_color_b_stop":{"unit":"%","size":100,"sizes":[]},"_background_color_b_stop_tablet":{"unit":"%"},"_background_color_b_stop_mobile":{"unit":"%"},"_background_gradient_type":"linear","_background_gradient_angle":{"unit":"deg","size":180,"sizes":[]},"_background_gradient_angle_tablet":{"unit":"deg"},"_background_gradient_angle_mobile":{"unit":"deg"},"_background_gradient_position":"center center","_background_gradient_position_tablet":"","_background_gradient_position_mobile":"","_background_image":{"url":"","id":"","size":""},"_background_image_tablet":{"url":"","id":"","size":""},"_background_image_mobile":{"url":"","id":"","size":""},"_background_position":"","_background_position_tablet":"","_background_position_mobile":"","_background_xpos":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_xpos_tablet":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_xpos_mobile":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_ypos":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_ypos_tablet":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_ypos_mobile":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_attachment":"","_background_repeat":"","_background_repeat_tablet":"","_background_repeat_mobile":"","_background_size":"","_background_size_tablet":"","_background_size_mobile":"","_background_bg_width":{"unit":"%","size":100,"sizes":[]},"_background_bg_width_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_background_bg_width_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_background_video_link":"","_background_video_start":"","_background_video_end":"","_background_play_once":"","_background_play_on_mobile":"","_background_privacy_mode":"","_background_video_fallback":{"url":"","id":"","size":""},"_background_slideshow_gallery":[],"_background_slideshow_loop":"yes","_background_slideshow_slide_duration":5000,"_background_slideshow_slide_transition":"fade","_background_slideshow_transition_duration":500,"_background_slideshow_background_size":"","_background_slideshow_background_size_tablet":"","_background_slideshow_background_size_mobile":"","_background_slideshow_background_position":"","_background_slideshow_background_position_tablet":"","_background_slideshow_background_position_mobile":"","_background_slideshow_lazyload":"","_background_slideshow_ken_burns":"","_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction":"in","_background_hover_background":"","_background_hover_color":"","_background_hover_color_stop":{"unit":"%","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_color_stop_tablet":{"unit":"%"},"_background_hover_color_stop_mobile":{"unit":"%"},"_background_hover_color_b":"#f2295b","_background_hover_color_b_stop":{"unit":"%","size":100,"sizes":[]},"_background_hover_color_b_stop_tablet":{"unit":"%"},"_background_hover_color_b_stop_mobile":{"unit":"%"},"_background_hover_gradient_type":"linear","_background_hover_gradient_angle":{"unit":"deg","size":180,"sizes":[]},"_background_hover_gradient_angle_tablet":{"unit":"deg"},"_background_hover_gradient_angle_mobile":{"unit":"deg"},"_background_hover_gradient_position":"center center","_background_hover_gradient_position_tablet":"","_background_hover_gradient_position_mobile":"","_background_hover_image":{"url":"","id":"","size":""},"_background_hover_image_tablet":{"url":"","id":"","size":""},"_background_hover_image_mobile":{"url":"","id":"","size":""},"_background_hover_position":"","_background_hover_position_tablet":"","_background_hover_position_mobile":"","_background_hover_xpos":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_xpos_tablet":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_xpos_mobile":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_ypos":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_ypos_tablet":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_ypos_mobile":{"unit":"px","size":0,"sizes":[]},"_background_hover_attachment":"","_background_hover_repeat":"","_background_hover_repeat_tablet":"","_background_hover_repeat_mobile":"","_background_hover_size":"","_background_hover_size_tablet":"","_background_hover_size_mobile":"","_background_hover_bg_width":{"unit":"%","size":100,"sizes":[]},"_background_hover_bg_width_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_background_hover_bg_width_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_background_hover_video_link":"","_background_hover_video_start":"","_background_hover_video_end":"","_background_hover_play_once":"","_background_hover_play_on_mobile":"","_background_hover_privacy_mode":"","_background_hover_video_fallback":{"url":"","id":"","size":""},"_background_hover_slideshow_gallery":[],"_background_hover_slideshow_loop":"yes","_background_hover_slideshow_slide_duration":5000,"_background_hover_slideshow_slide_transition":"fade","_background_hover_slideshow_transition_duration":500,"_background_hover_slideshow_background_size":"","_background_hover_slideshow_background_size_tablet":"","_background_hover_slideshow_background_size_mobile":"","_background_hover_slideshow_background_position":"","_background_hover_slideshow_background_position_tablet":"","_background_hover_slideshow_background_position_mobile":"","_background_hover_slideshow_lazyload":"","_background_hover_slideshow_ken_burns":"","_background_hover_slideshow_ken_burns_zoom_direction":"in","_background_hover_transition":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_border_border":"","_border_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_width_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_width_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_color":"","_border_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_radius_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_radius_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_box_shadow_box_shadow_type":"","_box_shadow_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"_box_shadow_box_shadow_position":" ","_border_hover_border":"","_border_hover_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_hover_width_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_hover_width_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_hover_color":"","_border_radius_hover":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_radius_hover_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_radius_hover_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_box_shadow_hover_box_shadow_type":"","_box_shadow_hover_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"_box_shadow_hover_box_shadow_position":" ","_border_hover_transition":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_switch":"","_mask_shape":"circle","_mask_image":{"url":"","id":"","size":""},"_mask_notice":"","_mask_size":"contain","_mask_size_tablet":"","_mask_size_mobile":"","_mask_size_scale":{"unit":"%","size":100,"sizes":[]},"_mask_size_scale_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_size_scale_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_position":"center center","_mask_position_tablet":"","_mask_position_mobile":"","_mask_position_x":{"unit":"%","size":0,"sizes":[]},"_mask_position_x_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_position_x_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_position_y":{"unit":"%","size":0,"sizes":[]},"_mask_position_y_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_position_y_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_repeat":"no-repeat","_mask_repeat_tablet":"","_mask_repeat_mobile":"","hide_desktop":"","hide_tablet":"","hide_mobile":""},"defaultEditSettings":{"defaultEditRoute":"content"},"elements":[],"widgetType":"image","htmlCache":"\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t","editSettings":{"defaultEditRoute":"content","panel":{"activeTab":"content","activeSection":"section_image"}}}]}](https://www.mitsuba-h.com/wp-content/uploads/2024/05/住活コラム_『リノベ済物件』or『買ってからリノベ』_4.jpg)
中古物件を購入してからリノベする場合の注意点を解説します。
1.物件探し・リノベ・住宅ローンの3工程がある
中古住宅を購入してからリノベしたい場合、「ワンストップ」という方法を取り扱っている会社に行けば、中古物件探しからリノベーションまで全ての工程をひとつの会社で行うことが出来ます。この場合はさほど手間はかかりません。
しかし、物件購入とリノベーションを別々の会社に依頼したい場合、注文住宅なみに手間がかかります。なぜなら、物件探し、リノベーション、住宅ローン、この3つをこなしていかなくてはならないからです。
流れとしましては、まずは不動産会社でリノベーション向き物件を探してもらいます。そして、物件の売買契約・決済・引き渡しが完了したら、別の会社でリノベーションの契約、工事へと進みます。
2.リノベできない中古物件もある
フルスケルトンでのリノベーションは、基本的には間取りや設備の変更が可能ですが、建物の構造によってはリノベーションが制限される場合もあります。具体的には、以下のような構造のマンションではリノベーションが難しいことがあります。
・耐震性や構造上、必要な柱は解体できない
・マンションの共有部分(外壁の塗装など)にはリノベーションはできない
・上下・左右の部屋に影響がない範囲で工事ができる
(そのため、床材の変更が禁じられているケースがあります)
・マンションの規約で電気とガスの容量が定められているため、オール電化に変更できない場合がある
物件を探す時は、不動産会社にリノベをしたいことを伝え、適した物件を探してもらいましょう。
5. 住宅ローンとリフォームローンの違い

最後に、住宅ローンとリフォームローンの違いを解説します。
住宅ローン…新築または中古住宅の購入や建築資金を賄うための融資。住宅の購入や建設に関連する費用をカバーします。
リフォームローン…既存の住宅のリフォームや改修、修繕のための融資。住宅の改装やリノベーションに関連する費用を支援します。
住宅ローン | リフォームローン | |
選択可能な金利 | 「変動金利型」「固定金利型」「固定選択金利型」から選択できる | 「変動金利型」(年2回金利見直し)が主流。金利が住宅ローンよりも高い。 |
返済期間 | 最長30〜35年 | 6ヵ月〜15年程度 |
対象物件 | 新築住宅や中古住宅、マンション、土地購入 | 既存の住宅のリフォームや改修、修繕 |
審査基準 | 審査期間は長め。完済時年齢、借入時年齢、返済負担率、勤続年数、年収、担保評価、健康状態などをみて審査する。 | リフォームの内容や予算、物件の価値などが審査の要件となる。 |
リフォームローンの金利は通常、2〜5%と高めに設定されています。一般的には、物件の購入には通常の住宅ローンを利用し、リノベーション費用には別途リフォームローンを利用するケースが多いです。
ただし、物件の購入とリノベーションを別々の会社に依頼する場合は、通常の住宅ローンとリフォームローンの二重ローンになります。このような二重ローンを避けたい場合は、一体型ローンを利用する方法もあります。
6. まとめ
『リノベ済物件』を選ぶメリットは、リノベの工程やコストの管理を気にする必要がなく、即入居が可能な点です。リノベ内容にこだわりがない場合や、時間や手間を省きたい場合に適しています。
一方で、『買ってからリノベ』の場合は、自分たちの好みやライフスタイルに合わせてリノベを行うことができるため、満足度が高い結果を得られる可能性があります。ただし、工事の管理やコストには注意が必要であり、入居までの期間が長くなる場合もあります。
どちらが良いかは、予算や時間、自分たちのニーズや希望によって異なります。具体的な条件や優先順位を考慮して、最適な選択を行うことが重要です。
コラム・住まい探しに役立つ情報

家が売れなかった場合の選択肢-原因と対処法も紹介
家の売却が困難な状況に陥った際、原因を把握し適切な対処法を見つけることが重要です。
多くの場合、不動産市場の動向や価格設定の適正さ、物件の魅力などが要因となります。
この記事では、売れ行きの低迷に至る原因やその対処法について解説します。
1.家が売れなかった場合の未来や選択肢

売却して家が売れなかった場合、最終的にどうなるのでしょうか。
1.空き家として残る
家が売れない場合、所有者はそのまま家を維持し、空き家として残すことができます。この場合、定期的なメンテナンスや税金、保険料などのコストがかかります。また、空き家が周囲の地域や地域全体の景観や安全性に影響を与える可能性があるため、地域社会や地方自治体にとっても懸念材料となることがあります。
2.不動産会社に買取してもらう
家が売れない場合、仲介ではなく不動産会社に買い取ってもらう「買取」という選択肢もあります。
買取では、仲介のように販売活動を行わずに、提示された査定額に納得すれば即売却となります。売却を急いでいる、またはなかなか買い手がつかない場合に有効な方法ですが、買取の場合は仲介よりも安く売却されることが一般的です。通常、相場の7~8割程度で買取されるとお考えください。
3.賃貸に出す
売れなければ賃貸やリースバックという選択肢もあります。まず、賃貸に出す場合は、家を貸すことで収入を得ることができますが、管理費用や修繕費用、家賃未払いなどのリスクを考慮する必要があります。また、家を売るという最初の目標を達成するために、再び売却を検討するタイミングが訪れます。
4.リースバックする
リースバックとは、家をリースバックの業者と「普通借家契約」または「定期借家契約」を締結し、その業者に毎月家賃(リース料)を払いながら住み続けるという売却方法のひとつです。売却しても家を失わず、固定資産税もかからないのでメリットが多い方法ではありますが、通常の売却よりも売却価格が安くなることがほとんどです。近隣の賃貸よりも家賃が高いこともデメリットとなります。
2.よくある「家が売れない」原因と対処法

次に、よくある家が売れない原因をいくつか挙げていきます。
1.家そのものに問題がある
築年数や立地、日当たりなど、物件の条件は売却に大きな影響を及ぼします。立地や周辺環境は不動産取引において重要な要素です。たとえば、交通の便が悪かったり、バスの本数が少なかったり、治安が悪い地域では、購入希望者が集まりにくい傾向があります。
さらに、内装や外観が劣化していたり、汚れていたり、手入れが行き届いていないと、物件が魅力的でないと見なされることがあります。同じ地域に状態の良い物件がある場合、買い手は魅力的な物件を選びたいと考えるでしょう。劣悪な状態の物件は競合物件と比較して不利になり、競争力が低下します。劣化がひどい部分だけでもリフォームをして、少しでも物件の良さをアピールしましょう。
2.売り出し価格が適正ではない
購買希望者は複数の物件を比較して検討します。相場を把握しているため、過剰な価格設定は他の物件と比較した際に選択肢から外れる可能性が高まります。逆に価格が安すぎる場合も、品質に対する疑問が生じ、購買希望者の興味を引き付けることができません。
中には、高い価格から段階的に価格を下げる戦略を取る方もいらっしゃいますが、実際にはこの方法が成功するケースはまれです。迅速な売却を望むのであれば、最初から適正価格を設定することが重要です。
3.物件の問い合わせや内覧希望者が少ない
適切な広告や宣伝が行われていない場合、物件が見過ごされる可能性があります。オンラインやオフラインの広告、不動産ポータルサイトやSNSなどを活用して、物件の情報を広くアピールすることが重要です。
売却をするなら集客力がある不動産会社を選ぶことをおすすめします。集客力は、販売活動の要です。物件情報の広告範囲が狭い不動産会社よりも、幅広い媒体で情報を発信する会社を選びましょう。不動産ポータルサイトやSNS広告、店頭展示、チラシなど、多角的なアプローチが購買希望者の注意を引く助けになります。
3. 内覧から購入に繋がらないのはなぜ?

内覧から購入につながらないケースが多い理由は、実際に物件を見た時に、写真とのギャップが大きいことが挙げられます。この問題を解決するには、物件の状態を向上させておくことが重要です。
まずは、家の中を徹底的に清掃し、清潔感を演出しましょう。生活感や不快なにおいは内覧者の興味を損なう可能性があります。内覧対応の際には、以下のポイントを心掛けてください。
・家の中の不要な物を一時的に別の場所に移動させる
・水回りの清掃は徹底的に行う(ハウスクリーニングも検討)
・場合によっては水回りのリフォームも検討する
手間や費用はかかりますが、内覧者の満足度を高めるために、物件の状態を向上させる努力は必要不可欠です。
4. 住宅ローンが残っている家が「売れない」場合

売却するにあたって、住宅ローンの残債はとても重要です。残債によって、選択すべき売却方法も変わってきます。
1.アンダーローンかオーバーローンか
住宅ローンが残っている家を売却する場合、アンダーローン(売却金額が残債よりも高い状態)であれば、売却金で残債を一括返済できるため、スムーズに売却手続きが進みます。しかし、オーバーローン(売却金額が残債を下回る状態)の場合は、自己資金を追加して完済してから売却するか、任意売却を選択することになります。ただし、任意売却には一定の期限があり、買い手が見つからずに売却できなかった場合には、競売にかけられてしまいます。次項から詳しく説明します。
2.仲介と買取以外を選択するなら「任意売却」の検討を
オーバーローンの場合、任意売却で済むのなら競売にかけられる前に行動を起こしましょう。売却価格の高さで順番に並べるなら、仲介、任意売却、買取、競売の順になります。任意売却は競売よりは高値で売却できる可能性があります。
仲介と買取以外の選択をするなら任意売却がベターです。
ただし、任意売却を選んだ場合でも、住宅ローンがゼロになるわけではなく、売却後も残債の返済が必要です。その場合、金融機関は一括返済を求めることはまれであり、分割払いの交渉は可能です。あきらめずに行動を起こしましょう。
3.住宅ローンが払えなければ「競売」になる
住宅ローンが残っている家が売れない場合、最終的には競売にかけられる可能性があります。
任意売却には一定の期限があり、買い手が見つからない場合は競売に進むことになります。競売はオークション形式で行われ、通常は相場の50~70%程度でしか売却されません。このため、希望価格での売却は保証されず、最悪の場合は負債が残ってしまい、自己破産に至ることもあります。競売には何らメリットはありません。住宅ローンが残っている家を売却する際には、競売以外の方法を検討し、専門家に相談して慎重に進めることが重要です。
5. 売却を成功させたいのなら不動産会社選びは慎重に

家の売却がうまくいかない一因として、不動産会社選びに失敗していることが挙げられます。
では、どのような不動産会社を選べばよいのでしょうか。大手不動産会社?それも間違いではないですが、ネームバリューだけで不動産会社を選ぶと失敗します。大手でも地域密着型でも、「提案力」「集客力」「販売力」、このどれかひとつでも足りない不動産会社は選ぶべきではありません。
まず、「提案力」は物件の適正価格を的確に提示する能力です。提案力のある不動産会社は、過去の取引データや市場動向を踏まえ、専門知識と現実的な評価を結びつけて適切な価格を示してくれます。
次に「集客力」です。これは販売活動の要です。物件情報の広告範囲が狭い不動産会社よりも、幅広い媒体で情報を発信する会社を選びましょう。不動産ポータルサイトやSNS広告、店頭展示、チラシなど、多角的なアプローチが購買希望者の注意を引く助けになります。
最後は「販売力」です。人気エリアの物件でも、営業担当の販売力が欠けていれば売却が難しいです。中古物件購入者は懸念や疑念を持ちがちですが、その不安を解消し、物件の魅力や良い側面を伝える力が肝要です。ネガティブな理由を前向きなポイントに変換し、購買意欲を喚起する能力が求められます。
6. まとめ
今回の記事では、家が売れない一般的な原因とその対処法について解説しました。家の売却が難航する理由は、物件自体に問題がある場合や、売り出し価格が適正でない場合など様々です。特に住宅ローンが残っている場合は、競売にかけられる前に他の売却方法を検討することが重要です。
ミツバハウジングでは、提案力、集客力、販売力を備えた専門チームが売却活動を行い、成約につなげます。売却を考えている方や既に売り出し中の物件についても、ぜひ当社にお任せください。
コラム・住まい探しに役立つ情報

【住宅の耐用年数】古い住宅を購入するメリットデメリットは?
住宅の耐用年数について理解することは、不動産売買の際に重要です。
住宅の資産価値は年月が経つにつれて変化し、その変化を知ることで将来的な購入や売却の判断がしやすくなります。
また、古い住宅を購入する際のメリットとデメリットもあわせて解説します。
1.住宅の耐用年数について

耐用年数は、大きく分けて以下の3種類があります。
1.法定耐用年数(耐用年数) 特定の資産や設備の減価償却費用を算出するために国が決めた年数のことです。建物の種類や構造、用途によって一律に定められています。この法定耐用年数によって建物の資産価値を判定します。
2.物理的耐用年数 建物自体が劣化し、構造物の仕組みや材質の品質が維持できなくなるなど、実際に使用できなくなるまでの年数を指します。これは建物そのものの耐久性や劣化の度合いを考慮し、構造的な要素や材料の品質が低下することによって示唆される耐用年数です。
3.経済的残存耐用年数 不動産が実際にどの程度継続して使用でき、不動産としての価値が低下し、最終的になくなるまでの期間を示します。これは物理的な劣化だけでなく、将来的な補修や修繕費用、建物の機能の見込まれる寿命も考慮されます。 |
この3つの中で最も目にするのが法定耐用年数ですね。法定耐用年数によれば、木造は22年、鉄骨鉄筋コンクリート造は47年とされています。
ここでひとつ注意していただきたいのは、法定耐用年数は税法の資産価値がゼロになるまでの年数を国が定めただけあって、実際に何年まで住めるのかを示しているわけではないという点です。法定耐用年数はあくまでも減価償却費※を算出する際に使うための数字で、法定耐用年数では22年や47年であっても、これ以上の期間も住み続けることが可能です。
※減価償却費とは?
詳しくは後述しますが、簡単に説明すると、『不動産の価値が減少することを考慮し、その減少分を毎年一定の割合で経費として計上すること』を減価償却費と呼びます。
1. マンション
マンションの税法上の耐用年数は、47年。コンクリート造だけあって、一戸建てに比べて耐用年数が長めです。
ちなみに、国土交通省の「中古住宅流通促進・活用に関する研究会」によれば、鉄筋コンクリート造建物の物理的寿命は推定で117年とされています。日本のマンションの歴史が浅いため、117年というのは推定に過ぎませんが、耐用年数である47年を過ぎてもなお、現役のマンションが多数存在しているのが興味深いですね。
先に説明したとおり、耐用年数は建物の寿命ではなく、税法上の資産価値がゼロになるまでの年数を示したものです。マンションの場合は特に寿命が長いので、耐用年数よりも資産価値で考えた方が分かりやすいかもしれません。
以下は、築年数による資産価値の変動をまとめたものです。
築10年以内: 新築の8割程度
築11~20年: 新築の6~7割程度
築21~30年: 新築の4割程度
築30年超: 新築の4割以下
マンションの資産価値は、築10年以内には新築の8割程度まで下落し、築15年頃には下げ止まります。マンションは築浅なほど需要が高まるため、売却を考える際には築6~15年の間が売り時とされています。購入後5年以内の売却は赤字になるケースは多いですが、マンションを売却するなら早めのご検討をおすすめします。
2. 木造一戸建て
木造住宅はメンテナンスや造り方によって寿命が左右されますが、22年を過ぎてもなお現存する住宅は数多く存在します。また、いくつかのハウスメーカーでは60年保証や100年住宅といった取り組みも見受けられます。
以下は、木造一戸建ての築年数による資産価値の動きをまとめたものです。マンションと比較すると資産価値の下落スピードが速いのでビックリする方も多いかもしれません。
築10年以内: 新築の5割程度
築11~20年以内:築15年で新築の2割程度
築20年超: 資産価値はほぼゼロ
一戸建ての場合はマンションに比べて資産価値の減少スピードが速く、築10年以内には新築の5割程度、築15年を目安に下落幅がゆるやかになり、新築の2割まで下落します。そして築30年を超えると建物部分の資産価値はほぼゼロとなります。残る資産価値は土地です。
しつこいようですが、上記は建物の寿命ではなく、資産価値です。いつまで住めるかを表した数字ではありません。この点を勘違いしてしまうと「一戸建てはマンションよりも早く住めなくなる!」という認識になってしまいます。
確かに耐用年数はマンションの方が長いですし、木造よりも鉄筋コンクリート造の方が素材としては頑丈なのは間違いありません。しかし、管理状態によってはマンションよりも木造一戸建ての方が「建物としての状態が良好」なケースは多々あります。
2.耐用年数と減価償却の関係
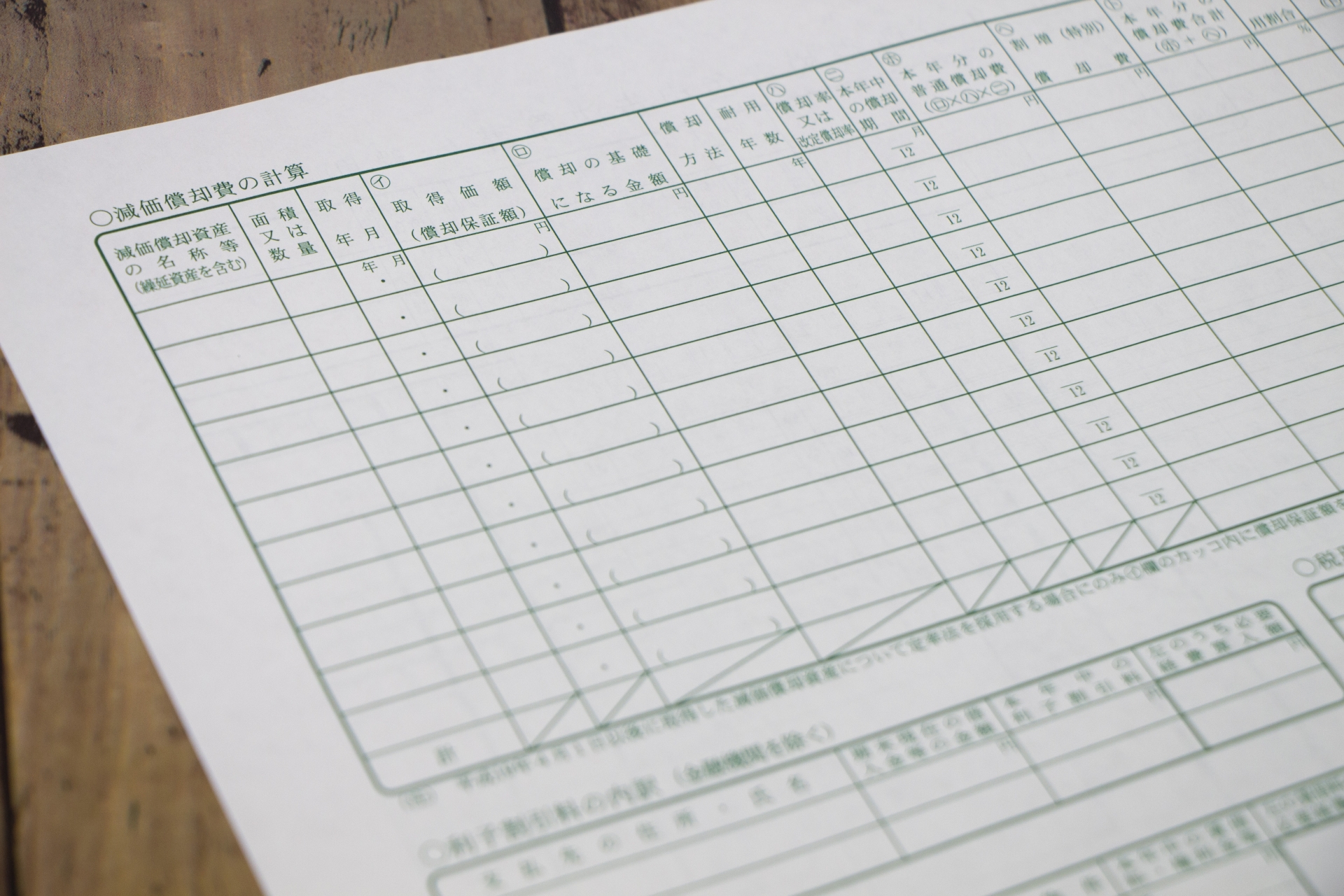
耐用年数は、税法上の資産価値がゼロになるまでの年数を示したものだと説明しました。もっと専門的な言い方をすると、耐用年数とは、減価償却を算出するための指標です。ちょっと難しい内容ではありますが、知っておいて損なことではありません。特に不動産売却を検討されている場合は、耐用年数と減価償却の関係についても知識を身につけておく必要があります。
1. 減価償却とは
減価償却とは、建物の価値が減少することを考慮し、その減少分を毎年一定の割合で経費として計上することを指します。
減価償却は時間の経過とともに価値が減少する前提に基づいているため、土地は減価償却に含まれません。
2. 減価償却を使う時はいつ?
減価償却の計算が必要なケースは、主に以下の2つです。詳しく見ていきましょう。
1.賃貸収入で得た収入を確定申告する時
アパートやマンションの経営によって得た賃料収入は、不動産所得として確定申告が必要です。この不動産所得には所得税が課されますが、建物の価値が経年劣化する分を「減価償却費」として賃料収入から差し引くことができます。これにより所得税の節税が可能となりますので、減価償却費の計上を忘れずに行うことが重要です。
2.不動産を売却する時
不動産を売却して得た利益は「譲渡所得」として所得税や住民税の対象になります。この際、譲渡所得の計算には建物の取得費が必要です。土地は年月が経っても価値が減少しないので、購入価格がそのまま取得費になります。
取得費とは、建物の購入代金とそれに関連する諸費用の総額を指します。譲渡所得の計算式は、収入金額から(取得費から減価償却費を差し引いた額)と譲渡費用を差し引きます。
3. 減価償却の計算方法
不動産を住居用として取得した場合の減価償却計算方法を解説します。
減価償却には「定額法」と「定率法」という2つの方法があります。
・定額法 耐用年数の期間内において毎年一定の金額を減価償却する方法です。この方法では、年数が短いほど利益が残りやすい特徴があります。 計算式:減価償却費=取得価格×定額法の償却率 ・定率法 未償却の残高に対して毎年一定の割合を適用し減価償却する方法です。初期の方で多くの減価償却費がかかり、年々低減していきます。 計算式:減価償却費=未償却残高×定率法の償却率 |
償却率は国税庁「減価償却資産の償却率等表」で確認できます。
3.古い住宅を購入するメリット

ここまで住宅の耐用年数や減価償却について解説しましたが、築年数が経過した古い住宅を購入するメリットもおさえておきましょう。
1. 新築よりも安く手に入る
新築の住宅は施工や設備が最新である一方で、その分価格も高額です。一方で、築年数が経過した古い家は、新築に比べて安く手に入ることがあります。
ただし、リフォームやメンテナンスに投資が必要な場合があるため、トータルのコストを検討することも重要です。
2. 物件数が豊富
家を建てられる土地は限られています。そのため、これから建つ新築の数よりも、今すでに建っている中古住宅の方が多いのは当然ですね。
中古住宅も視野に入れれば、選択肢がぐっと増えます。歴史や個性を感じることができる古い住宅も多く、自分の好みやライフスタイルに合った住宅を見つけやすい点もメリットです。
3. リノベーションを楽しめる
古い住宅は時間の経過とともに変化し、その歴史や個性が感じられます。古い建材やデザインを活かしながら、自分だけのオリジナルな住まいを実現することができます。
ただ、中古住宅購入+リノベーションを行うことで新築住宅よりもコストがかかる可能性もありますので、資金計画は慎重に行いましょう。
4.古い住宅を購入するデメリット

続いて、古い住宅を購入するデメリットを解説します。
1. 老朽化が気になる
古い住宅の場合、屋根や壁、設備だけではなく、電気配線や配管なども古くなっていることがあります。老朽化が進んでいる場合、メンテナンスやアップグレードにかなりの費用がかかる可能性があるため、注意が必要です。
老朽化のチェックは、一般の方には困難です。不安な方は、住宅診断(ホーム・インスペクション)を検討することをおすすめします。
2. 設備の機能性が新築よりも劣る
古い住宅は、新築に比べて最新の設備や機能が備わっていないことが一般的です。特に、キッチンやバスルーム、暖房設備などは年月が経つにつれて進化しているため、効率性や快適性において新しい物件に及ばないことがあります。
また、省エネ性やセキュリティの向上など、現代の住まいに求められる要件が満たされていない可能性もあります。
。
3. 将来売却しても売れにくい可能性がある
古い住宅は、耐用年数が進んでいるため、将来的に売却する際に魅力を保つことが難しい可能性があります。
同じ価格帯で新しい物件が出てきた場合には競争が厳しくなりますし、古い住宅には修繕やリノベーションが必要な場合があり、これにかかる費用も買い手にとってネガティブな要素となり得ます。
4.まとめ
今回の記事では、主に住宅の耐用年数と古い家を購入するメリットデメリットを解説しました。繰り返しになりますが、住宅の耐用年数は、あくまでも減価償却費を算出する際に使うための数字で、実際に何年まで住めるのかを示しているわけではありません。
耐用年数を過ぎた家でも快適に住める住宅は多数あります。中古住宅を探している、という方はぜひ一度ミツバハウジングまでお問い合わせください。
コラム・住まい探しに役立つ情報
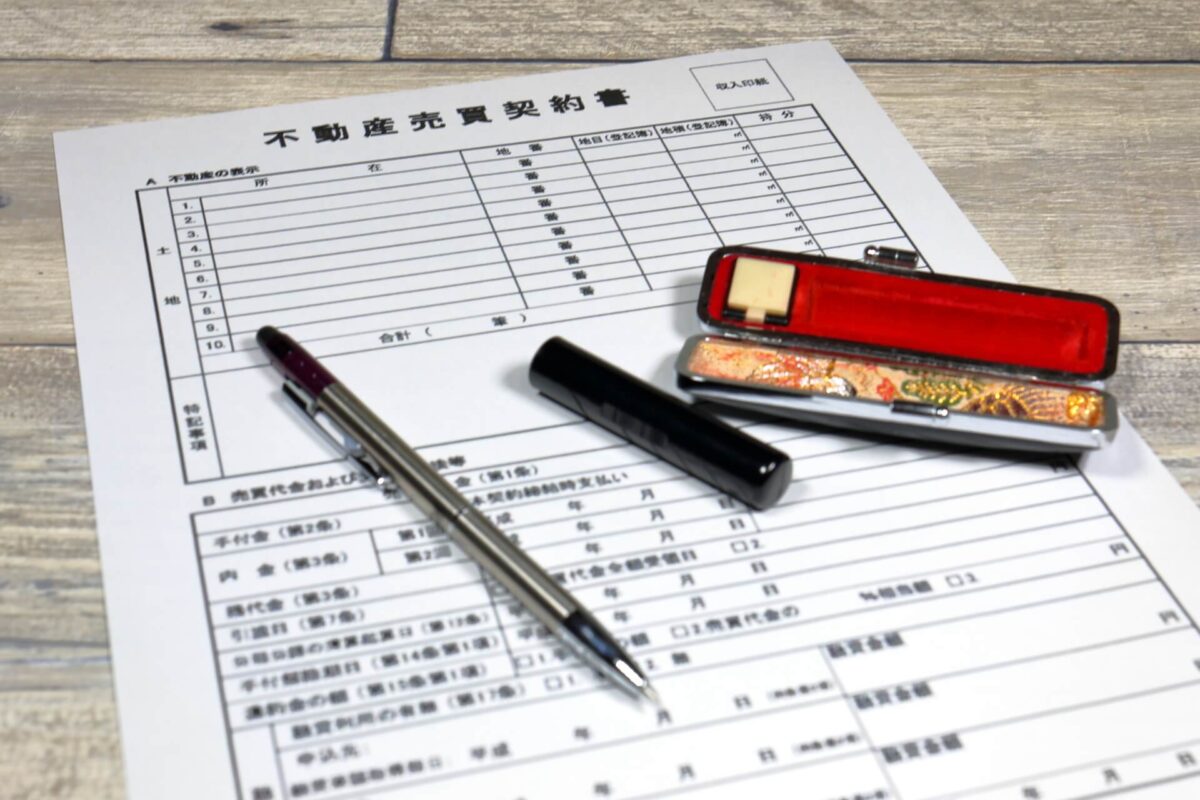
売却で成功するためのポイント 売れやすいタイミング
不動産を売却する際、最も重要なのは売れやすいタイミングを見極めることです。この記事では、売却で成功するためのポイントと、物件を売りやすくするタイミングに焦点をあて、理想的な条件で不動産を売り抜くためのアドバイスをお届けします。
1.売却で成功するためのポイント

まずは、売却で成功するためのポイントを解説します。
1.不動産会社は査定額だけで選ばない
高い査定価格を出してくれたからといって、その不動産会社が優れているとは限りません。また、必ずしも売り出し価格と一致するわけでもありません。
不動産会社によって査定価格がバラバラなので、高い査定を提示した会社を選んでしまう気持ちは理解できますが、それは大きな間違い。売却を任せて欲しくて、相場より高い査定価格を提示する不動産会社も存在します。
査定額だけで判断せず、実績と信頼性を持つ不動産会社を選ぶことが重要です。
2.売却する希望価格と最低価格を決めておく
不動産を売却する際に多くの人が直面する難題は、「売りたい価格」と「売れる価格」の差です。少しでも高く売りたいのはみなさん同じで、実際に売れる価格とのギャップに悩みます。
売却で成功するために最初に考えるべきは「最低ライン」の価格です。これはローン残債や売却にかかる費用などを考慮した金額です。「これ以下の価格での売却は難しい」という最低ラインの価格を把握したら、それを基準にして「売りたい価格」や不動産会社の「査定額」と比較してみましょう。もし「最低ライン」よりも「査定価格」が低い場合は、売却自体を再考する必要があります。
3.売却理由は正直かつポジティブに伝える
家を売却する理由は、人によって様々です。物件そのものに問題がある場合や、転勤、離婚、子どもが自立後の住み替えなど、その理由はたくさんあります。
買主が購入を迷う売却理由として多いのは
・物件そのものに問題がある
・近隣に店や病院などがなくて不便そう
・騒音や日当たりに問題がある
・近隣の治安が悪い
などです。
これらの理由はネガティブなイメージに繋がりやすいですが、隠さずに正直に伝えましょう。その際は、物件のアピールポイントや、「こういう風に生活すると快適ですよ」といった具体的な提案をすることも重要です。
たとえば、この窓は西日がきついので遮光カーテンをつけると良いとか、少し歩くと安いスーパーがある、などといった提案です。隠すよりも物件のネガティブな面に向き合っている姿勢を示すと買主からの信頼を得られるでしょう。
特に離婚による売却は珍しくもなく、むしろ多いぐらいなので、隠す必要はありません。購入希望者の中には縁起をかつぐ方もいらっしゃるので、離婚で売却された物件は買いたくないという場合もありますが、隠すよりも正直に伝えた方がスムーズに売却が進む可能性が高いです。
4.知識を身につけて不動産会社に丸投げしない
不動産の売却手続きは基本的に仲介会社に委ねることができますが、売却での成功を望むなら、基本的な不動産売却の知識を身につけておくことが重要です。自身で売却の流れや物件の相場、周辺地域の情報の収集をしておき、不動産会社に完全に頼り切らないようにしましょう。
同時に、買主の視点を考慮することも重要です。物件の魅力や内覧時に注目されるポイント、不安や質問が出る可能性がある事柄などを買主目線で考え、それに基づいて物件を魅力的にアピールする工夫が求められます。
5.売れにくい物件は専任媒介契約で売る
「都市部から離れている」「駅からの距離が遠い」など、売れにくいと感じる物件には、専任媒介契約がおすすめです。
「売れにくい物件なら、複数の不動産会社と契約すれば早く売れるのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には専任媒介の方が多くの場合において有利なのです。
一般媒介契約では、複数の不動産会社が関与するため、売却に積極的に取り組みにくくなり、結果的に売却期間が延びる可能性があります。専任媒介契約では、売主が一社に売却を委託することで、その不動産会社が独占的に売却活動を行います。これにより、迅速な売却が期待できます。
6.物件をきれいにしておく
物件をきれいにしておくことは、査定や内覧の際にも大きな影響を与えます。
一見するだけで気持ちよく感じる清潔な状態は、買い手に好印象を与えるだけでなく、物件の魅力を引き立てます。床や壁、窓など、細部にわたり手入れを怠らず、不要な物は片付けることで、広々とした印象を醸し出します。
物件の魅力を引きてる方法としては、以下の方法があります。すべて実行できなくても、徹底的に掃除をして清潔感を大事にしましょう。
・荷物を一時的にトランクルームに預ける
家の中がきれいであっても、物が多いと魅力的に見えません。物が多い方は、一時的にトランクルームに預けることをおすすめします。
・ハウスクリーニングを頼む
内覧者がイメージダウンする原因として一番多いのは水回りの汚さです。費用はかかりますが、水回りだけでもハウスクリーニングを検討してみてはいかがでしょうか。
・水回りだけでもリフォームする
ハウスクリーニングよりもさらに費用はかかりますが、汚れや劣化がひどい場合は水回りだけでもリフォームしても良いかもしれません。バスルームを丸ごと新しくする場合、おおよそ150万円ほど。水回り全体を一新する場合には、約200万円程度の費用がかかります。
2.家が売れやすいタイミング

売り時を見逃さないためには、家の売却タイミングを見極めることが不可欠です。特に悩まれるのが「今、売却しても大丈夫なのか?」という疑問。この章では、家が売れやすいタイミングを解説します。
1.成約件数が多いのは3月
賃貸繁忙期は1~3月と言われていますが、売買においては季節よりも需要の変動が少ない傾向があります。
しかし、春は入学シーズンで引っ越しを考える人が多いため、12月後半~1月に物件を出すことが効果的です。この時期にPRを施すことで、早期に高値での売却が期待できます。
2.マンションと築15年以内の一戸建ては早めに売る
一戸建ては築10年、マンションは築15年を境に購入需要が急激に減少します。これは、物件が古くなるにつれてメンテナンスやリフォームの必要性が高まり、それに伴って購入に対するハードルが上がるためです。
特にマンションは新築時のプレミア感が強く影響します。築浅であればあるほど、その新しさと良好な状態が需要を高め、高値での売却を容易にします。築15年以内の一戸建ても、早めに売却を検討することで市場での競争力を保ちます。
以下は、築年数ごとのマンションと一戸建ての資産価値と需要についてのまとめたものです。マンションや築15年以内の一戸建てを所有している場合は、築浅の状態を活かし、早い段階で売却を検討すると良いでしょう。
マンションの場合
築年数 | 資産価値 | 需要 |
築10年以内 | 新築の8割程度 | 需要が多く高値で売れやすい。 |
築11~20年 | 新築の6~7割程度 | 劣化が気になる箇所が出てくる時期で、安く買いたい層に需要あり。 |
築21~30年 | 新築の4割程度 | 修繕やリフォームによって価格が左右される。 |
築30年超 | 新築の4割以下 | 人気エリアや利便性の高い物件は需要がありつつも、築浅の物件と比較すると資産価値が下がる。 |
一戸建ての場合
築年数 | 資産価値 | 需要 |
築10年以内 | 新築の5割程度 | 需要は高い。さらに、省エネ住宅や人気のハウスメーカーが建てた住宅は、資産価値の下落幅が緩やかになることがある。 |
築11~20年以内 | 新築の2割程度 | 築15年を目安に下落幅が緩やかになる。 |
築20年以内 | 新築の2割程度 | 建物部分の資産価値はほぼなくなり、「古家付きの土地」として土地のみの価格で売買されるのが一般的。 |
3.不動産価格が高騰している時に売る
一般社団法人不動産協会「不動産関連データ」によれば、首都圏のマンション価格は2022年に6,288万円となり、前年比で0.4%上昇しました。2018年の平均価格から見ても、5年間で7.1%の上昇があります。
特に注目すべきなのは、2021年時点で既に1990年の不動産価格バブル期を上回っているという点です。ただし、現在の値上がりは急激なバブルとは言えないため、1990年代のような急激な価格の下落は予測しづらい状況です。
このような背景から、不動産価格が高騰している時期は、売却時に高い価格で取引できる可能性が高まります。購入希望者が増加し、需要が高まる中で売却を検討することで、良い条件での取引が期待できます。しかし、市況は変動するため、慎重な計画と柔軟な対応が求められます。
3. 所有期間が5年以下の家を売る場合の注意点

家を所有していた期間が5年以下か5年超かで、所得税と住民税の税率が大きく異なります。
所有期間 | 所得税率 | 住民税率 |
短期譲渡所得(5年以内) | 30.6% | 9% |
長期譲渡所得(5年超) | 15.315% | 5% |
上記の表を見ると分かるように、所有期間が5年以下か5年以上かで税率が約2倍もの差を生じます。特に注意が必要なのは、「5年以内」という認識の間違いです。所得税や住民税の計算は、「家を売却した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えていたかどうか」で判断されます。購入してからの住んでいた年数でなく、1月1日時点での所有期間が基準となるため、計算ミスには十分ご注意ください。
4. まとめ
今回は、売却で成功するためのポイント売れやすいタイミングについて解説しました。
売却のお悩みは、ミツバハウジングまでご相談ください。地域に特化した強みを持っているだけではなく「マーケティング&広告専門チーム」が適切な媒体に販売活動を仕掛け、圧倒的な集客を行います。そして、販売力のある営業マンが売主様に代わり、売却をスムーズに進めさせていただきます。メールでもお電話でも、お気軽にお問い合わせください。
コラム・住まい探しに役立つ情報

不動産売却時の流れを詳しく解説!
1.売却する時の全体的な流れ

まずは、不動産売却する時の全体的な流れを説明します。
全体的な流れ | 期間(6ヶ月が目安) |
家の相場を調べる | 約2週間~1ヶ月 |
査定依頼をする | |
媒介契約を結ぶ | |
売り出し価格を決める | |
売却活動スタート | 約3ヶ月 |
内覧対応 | |
売買契約を結ぶ | |
引き渡し・決済 | 約1~2ヶ月 |
仲介で売却する場合、一般的に3~6ヶ月かかると考えておきましょう。
最初の段階では不動産会社の選定や査定依頼、媒介契約の締結に1~4週間かかります。その後、買主を見つけるための売却活動や内覧対応などが1~3ヶ月かかり、最終的に売買契約が成立します。取引が進んだ後も、物件の引き渡しと決済には1~2カ月ほどの期間が必要です。
ただし、買主探しが難航すれば、さらに時間がかかることもありますし、特定の不動産によっては隣接する不動産との境界線を明らかにするために測量が必要な場合もあり、その際も時間がかかる可能性があります。
2.売却までの8つのステップ

売却活動の流れは、主に以下の8ステップです。
1.物件の相場を調べる
売却活動を始める前に、自分の物件がいくらで売られているのか相場を調べておきましょう。相場を調べるには、「レインズマーケットインフォメーション」と「土地総合情報システム」で調べる方法があります。
・レインズマーケットインフォメーションで調べる
レインズマーケットインフォメーションは、公益財団法人不動産流通機構が運営している全国の不動産取引情報を閲覧できるサイトです。通常の「レインズ」とは異なり、不動産会社に限らず一般の方も利用可能です。ただし、具体的な不動産取引の詳細情報は表示されず、成約時期や築年数などの詳細は伏せられています。利用者は以下の項目を調べることができます。
価格:百万円単位で表示され、十万円単位を四捨五入。 単価:万円/m2で表示され、小数点以下は四捨五入。 面積(建物・土地): 実際の面積に20m2の幅を持たせて表示される。面積が200m2を超える場合は「200m2超」と表示される。 築年数:実際の築年に2年の幅を持たせて表示される。 成約時期:成約された年月を3カ月で区切った範囲で表示される。 |
・土地総合情報システムで調べる
土地総合情報システムは、国土交通省が管理している不動産の取引価格や地価公示、都道府県地価調査の価格が閲覧できるサイトです。このサイトも、レインズマーケットインフォメーションと同じく、一般の方でも利用可能ですが、物件の詳細情報は非表示となっています。
掲載されている物件の内容には、「所在地」「最寄駅」「取引総額」「坪単価」「面積」などが含まれています。ただし、物件の所在地に関しては、町名までしか表示されません。
2.査定依頼をする
不動産会社の査定には、「簡易査定(机上査定)」と「訪問査定」があります。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
簡易査定…実際に不動産を見ずに、物件概要などから簡易的に査定する方法。
訪問査定…実際に不動産を見て査定する方法。
簡易査定は手軽で結果が素早く出ますが、訪問査定に比べて査定価格の正確性には限りがあります。一方、訪問査定は時間がかかる(1~2日後、最大でも1週間以内)ものの、より詳細かつ正確な査定が期待できます。
3.媒介契約を結ぶ
売却を仲介してもらいたい不動産会社が決まったら、媒介契約を結びます。媒介契約には以下の3種類があります。
・一般媒介契約
一般媒介は、不動産取引において売主が複数の不動産会社に同時に物件の仲介を委託する契約形態を指します。複数の不動産会社による同時仲介が可能であり、販売活動の競争を生む一方で、不動産会社側から見ると、「他社で成約してしまう可能性があるため売却活動に熱が入りにくい」という心理も存在します。
・専任媒介契約
特定の不動産会社にのみ売却の仲介を依頼する契約形態です。他の不動産会社に同時に依頼することはできません。この契約では、一つの不動産会社が専念的に販売活動を行うため、売却の進捗管理やマーケティングが一貫して行われるメリットがあります。
・専属専任媒介契約
一番厳格な契約形態で、特定の不動産会社に対して独占的に売却の仲介を依頼する契約です。他の不動産会社への依頼は一切認められません。自力で買主や借主を見つけたとしても、その取引は不動産会社を介したものとみなされ、仲介手数料が発生します。売主の自由度が制約される面もありますが、その分、売却が早く決まる可能性が高まるとも言えます。
4.売り出し価格を決める
売出し価格は「売主の希望価格」で、成約価格は「売買が成立したときの価格」です。売出し価格のまま売れるとは限りません。むしろ、中古物件の売買では値引き交渉されることが通常です。
相場と査定額を参考に、売り出し価格を決めていきましょう。値引きされることを想定して、価格設定を高めにする方もいらっしゃいますが、このような方法はあまりおすすめできません。
「この物件を買いたいけど、もう少し安くなりませんか」と購入希望者から価格交渉をされた時に値下げをして、結果的に売れるなら問題ないです。
しかし、実際には高い価格で売りに出したら購入希望者が現れないケースがほとんどで、そうなるとポータルサイトに載せてある売り出し価格を下げることになります。物件を閲覧している側から見ると、「売れ残り感」が出てマイナスイメージが強くなってしまいます。最初から相場に近い売り出し価格を設定しておきましょう。
5.売却活動スタート
いよいよ売却活動のスタートです。不動産会社が売却活動をする際、主に以下の方法で物件情報をPRします。
・不動産ポータルサイトへの掲載
主要な不動産情報サイトやポータルサイトに物件情報を掲載し、広く検索されやすくします。魅力的な写真や物件詳細などを掲載して、オンラインでの物件検索者にアピールします。
・物件チラシのポスティング
不動産会社が作成した物件チラシを地域のポスティングに活用し、興味を引くような情報をわかりやすく掲載します。
PR力がない不動産会社は、掲載する写真が下手だったり、物件のアピールポイントを魅力的に説明できなかったり、ポスティングの数も少ないことがあります。いくら物件が魅力的であっても、売却活動が適切でなければ買主は現れません。
特に一般媒介の場合は、「他社で成約するかもしれない」という不動産会社側の心理が働き、売却活動に熱が入りにくいことがあります。
6.内覧対応
中古物件の購入希望者の多くは、古くて生活感がある物件が欲しいわけではなく、「できるだけ新築に近いきれいな物件」が欲しいと考えています。ご自身がフリマアプリなどで商品を買う時の心理を思い出すと分かりやすいでしょう。
たとえ築年数が古くても、きれいに管理してある物件は好印象です。逆に言えば、築浅の物件であっても管理や清掃が行き届いていなければ、買い手はなかなかつきません。
特に注意したいのは、水回りです。できればプロに頼んでクリーニングしてもらいましょう。とにかく生活感をなくすことが重要です。掃除ももちろんですが、物が多いのもいけません。物が多い方は断捨離をするか、一時的にトランクルームに預けるのもおすすめです。
7.売買契約を結ぶ
買主との交渉がまとまったら売買契約を結びます。契約書の内容を確認し、不動産の基本情報や売買金額、引き渡し日、その他の条件に誤りがないかを確認しましょう。
また、買主から手付金をこの段階で受け取ります。手付金の金額は買主との協議に基づきますが、通常は売買価格の10%が相場です。残りの金額は引き渡しの際に受領します。
買主だけではなく、売主も支払う費用があります。代表的な費用は仲介手数料です。不動産会社に売却活動をしてもらい、成約となった場合は、不動産会社に仲介手数料を支払います。仲介手数料の上限は、以下の表のとおりです。
売買価格(税込) | 料率(税抜) |
200万円以下の部分 | 5% |
200万円超400万円以下の部分 | 4% |
400万円超 | 3% |
不動産の売買取引では、200万円を超えることが多いかと思います。そのため、仲介手数料は「売買価格×3%+6万円+消費税」となります。
仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約が成立した時点で50%、引き渡し完了時に残りの50%を支払います。
8.引き渡し・決済
通常、売買契約から約2週間から2ヶ月後に、引渡しと決済が同日に執り行われます。場所は買主の住宅ローンが取り決められた金融機関で、平日の午前中に実施されることが一般的です。
・引渡し 買主が売主に売買代金を支払い、売主は売買代金の受領と引換えに買主に物件を引き渡します。引渡しといっても物件そのものは動かすことができないため、当日は家の鍵や書類の受け渡しを行います。 ・決済 買主が売主に売買代金(手付金を引いた残代金)を支払います。住宅ローンを利用する場合は、指定口座に入金されます。 |
引き渡しの際、具体的に渡すものは以下のとおりです。
・物件の鍵
・新築時の図面一式
・設備のパンフレットや説明書
・建築確認通知書
・マンションの場合は組合規約
3. まとめ
今回は、不動産売却時の流れを詳しく解説しました。売主は買主に比べて必要な書類が多く、物件の退去作業なども迅速に進める必要があります。引渡し日に向けて計画を立てる際には、充分な準備とスケジュールの調整が欠かせません。引渡し日を基準に逆算して、早めに行動しましょう。